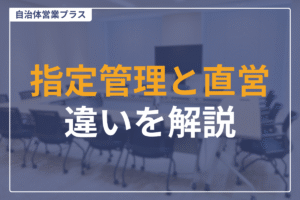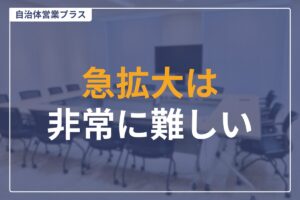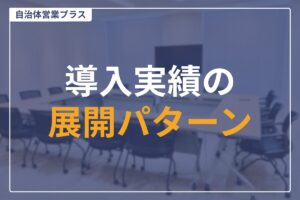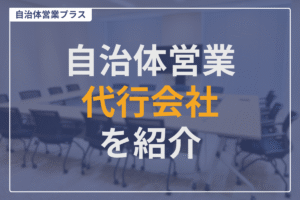自治体の役職構造について。主任・主事から始める営業の基本を解説
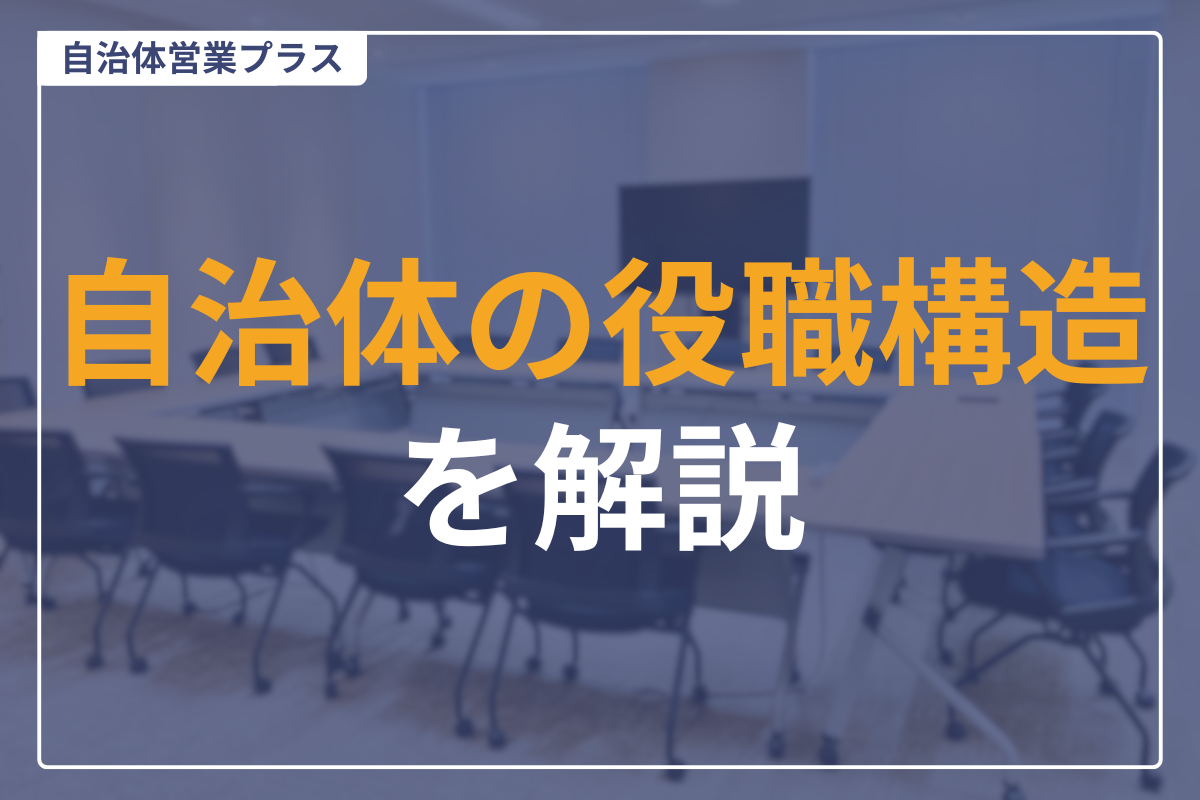
- URLをコピーしました!
はじめに
 木藤昭久
木藤昭久こんにちは!リクロスの木藤です。
今回は、自治体の役職構造について書いていきます。
民間とは異なる階層や名称が並び、「課長が意思決定者」「係長が実務のリーダー」といった表面的な理解では、的確な営業ができません。
私の自治体&自治体営業の経験上、最初の接点となるのは主任・主事といった一般職員クラスであることが多いです。
本記事では、営業現場のリアルに即して自治体の役職名と役割、営業の際に意識すべき点についてまとめます。
それでは見ていきましょう!
自治体の役職構造
まず、自治体の典型的な役職を整理します。
| 役職名 | 主な役割 | 営業との関係性 |
|---|---|---|
| 首長(市長・町長など) | 自治体の最高責任者。政策方針や予算編成を担う。 | 大型案件やトップダウン施策で関与。通常営業では接点は少ない。 |
| 副市長・副町長 | 首長の補佐役。各部の統括、庁内調整を行う。 | 部長レベルと連携して大規模施策を動かす。 |
| 部長・局長 | 分野ごとの行政を統括。予算と人員を管理。 | 高額・重要案件次第では最終的な決裁者となる。 |
| 次長・参事 | 部長の補佐、複数課にまたがる調整も行う。 | 提案内容の方向性や必要性を判断する役割。 |
| 課長 | 課の責任者。予算や事業の最終判断を行う。 | 決裁という形で成約までに必ず関与してくる。 |
| 課長補佐・主幹 | 課長の補佐役。業務・人員の調整や内部調整を担う。 | 直接の担当者(営業対象)となることもある。 |
| 係長・主査 | 実務のリーダー。チームマネジメントや調整を担う。 | 商談に同席することも珍しくない。信頼を得れば庁内展開が進む。 |
| 主任・主事 | 実務担当者。日々の業務を最前線で支える。 | 最初の接点となることが多い。 |
自治体によって名称と役割がズレることがありますが、ズレるとしても一列程度であることが多いですです。例えば、「主査が主任とほぼ同等の役割」などです。
営業の際に意識すべき点
次に、営業の際に意識すべき点を書いていきます。
①スタートは主任・主事から
営業現場で最初に応対してくれるのは主任や主事であることが多いです。
- 問い合わせ電話を受ける
- 提案資料に目を通す
- 担当業務に関連するかどうかを判断する
といった初動のほとんどを、主任や主事が担っています。
主任や主事の信頼を得られれば「係長に相談してみます」「課内で共有します」といった動きにつながります。逆に、ここで納得感が得られないと、それ以上の進展は望みにくくなります。
②係長や課長へと段階的に提案を上げていく
主任・主事からの上申が発生すると、次に登場するのが係長や主査といった実務の中堅層です。業務内容を熟知しており、導入の現実性を見極める立場にあります。
なお、係長・主査は自治体営業する際に必ずしもやり取りするとは限りません。主任・主事との商談だけで後は勝手に予算要求が進むこともあります。
そのうえで、一定の規模や予算を伴う提案であれば課長補佐や課長クラスが商談の場に出てくることもあります。弊社のお客様もいきなり部長と打ち合わせしたこともあるようなので、参加者は事前に伺っておくとよいでしょう。
なお、首長や部局長へのトップアプローチについては別途記事がありますので是非ご覧ください。
また、アプローチ先の部署がそもそも間違っていないか要確認です。
最後に
自治体の役職について書いてきました。
自治体営業では、いきなり上層部にアプローチしても簡単には動きません。現場(主任・主事)へのアプローチに再現性を持たせて他の自治体にも展開していくことが重要だと考えています。
現場の接点を大切にし、地道に関係を築いていくことが結果的に近道となるでしょう。
今回もお読みいただきありがとうございました。
- URLをコピーしました!