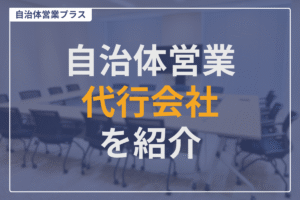指名競争入札とは?自治体でよくある他入札方法との違いとメリットを解説
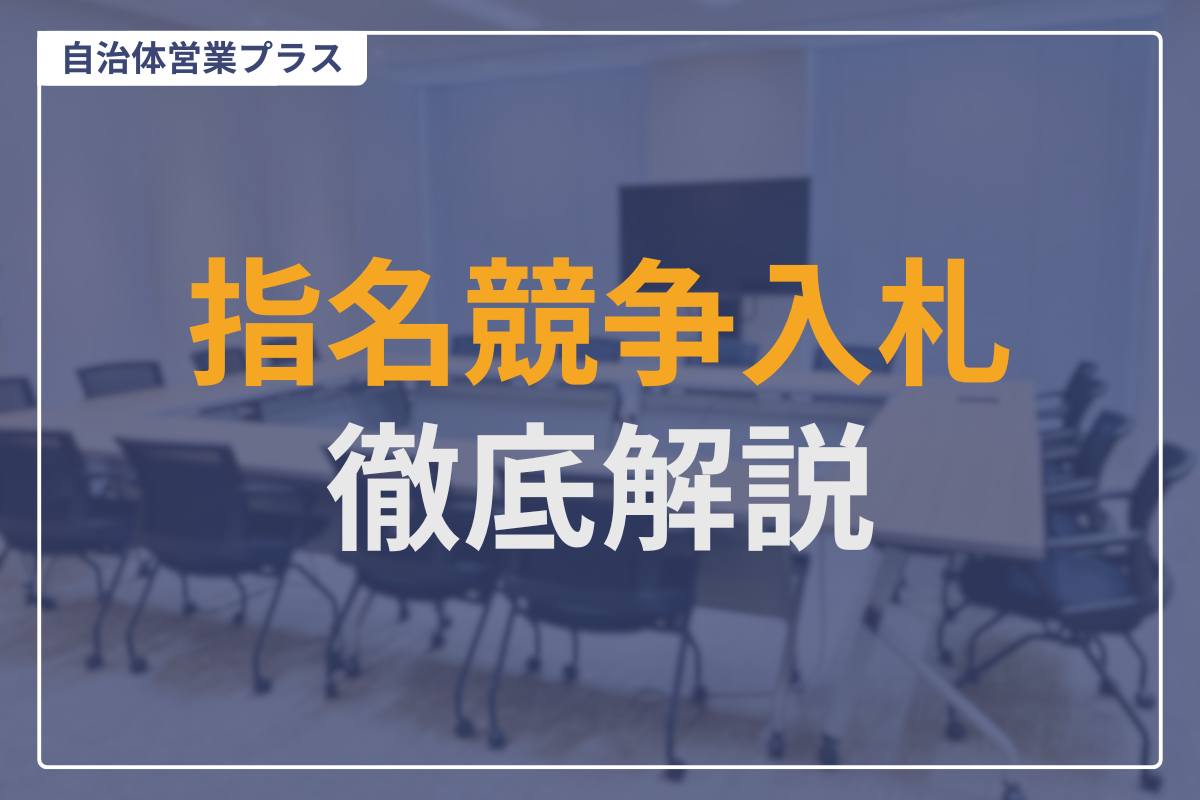
- URLをコピーしました!
「他の入札方法との違いがよくわからない」
「指名競争入札に参加したいけれど、どんな条件が必要なのだろう」
官公庁や自治体の入札に参加を検討する際、このような悩みはありませんか。入札には複数の方式があり、それぞれの違いを正確に理解しなければ、どの案件に注力すべきか判断が難しくなります。
この記事では、指名競争入札の基本的な仕組みから、他の入札方法との明確な違い、そして参加するメリット・デメリットまで詳しく解説します。
最後まで読めば、指名競争入札への理解が深まり、自社が参加すべきかどうかの判断基準が明確になるでしょう。
指名競争入札への参加をご検討の場合は、ぜひ株式会社リクロスへご相談ください。
指名競争入札とは?

指名競争入札は、国や地方公共団体などの発注機関が、あらかじめ選定した事業者だけが参加できる入札方法です。
発注機関が「この企業なら安心して任せられる」と判断した事業者に入札の参加機会が与えられます。
この方式の最大の特徴は、過去の実績や技術力が評価され、信頼性があると認められた事業者だけが指名される点です。
そのため、指名競争入札への参加資格を得るには、これまでの事業で培った確かな業績が非常に重要な要素となります。
誰でも参加できるわけではなく、いわば「招待制」の入札と考えるとわかりやすいでしょう。
指名競争入札と異なる入札方法の違い

指名競争入札の他にも、いくつかの入札方法が存在することはご存知でしょうか。それぞれの特徴を知ることで、自社がどの入札方法を目指すべきか戦略を立てやすくなります。
ここでは、代表的な入札方法である以下の3つと指名競争入札との違いを解説します。
- 指名競争入札と一般競争入札との違い
- 指名競争入札と公募型プロポーザルとの違い
- 指名競争入札と随意契約との違い
それぞれの違いを詳しく見ていき、自社に合った案件を見極めましょう。
指名競争入札と一般競争入札との違い
指名競争入札と一般競争入札の最も大きな違いは、入札に参加できる事業者の範囲です。
一般競争入札は、参加資格を満たせば不特定多数の事業者が誰でも参加できる、オープンな入札方法を指します。
発注機関は、最も良い条件を提示した事業者と契約を結ぶため、公平性が保たれやすいのが特徴です。
これに対して、指名競争入札は発注機関から指名された事業者しか参加できません。
指名競争入札と公募型プロポーザルとの違い
指名競争入札と公募型プロポーザルは、契約相手を選ぶ基準が異なります。指名競争入札では、提示された金額や内容を総合的に評価して落札者を決定します。
これに対し、公募型プロポーザル方式は、価格だけでなく事業の実施方針や体制、過去の実績といった要素を重視して契約相手を選ぶ方法です。
特に、専門的な知識や創造性が求められる業務で採用されるケースが多く見られます。案件は広く公示され、参加を希望する事業者の中から選定が行われます。
指名競争入札と随意契約との違い
指名競争入札と随意契約の違いは、「参加できる事業者の範囲」と「契約相手の決定方法」にあります。
指名競争入札に参加するためには、まず発注機関に技術資料などを提出し、指名基準を満たしていると判断される必要があります。
その後、指名通知を受けた事業者だけが入札に参加できるのが指名競争入札の特徴です。
一方、随意契約は発注機関が特定の事業者を選び、直接見積書の提出を依頼する方式です。そのため、発注機関からのアプローチがなければ契約の機会そのものがありません。
指名競争入札の種類

指名競争入札は、事業者の選定方法によって、いくつかの種類に分けられます。ここでは、主に以下の3つの種類について、それぞれの仕組みと特徴を解説します。
- 公募型指名競争入札
- 簡易公募型指名競争入札
- 工事希望型指名競争入札
自社の事業規模や得意分野に合わせて、どの種類が適しているか確認しましょう。
公募型指名競争入札
公募型指名競争入札とは、発注機関が示した参加条件を満たす事業者が、自ら参加の意思を表明する入札方法です。
この方式の一般的な流れは、まず事業者が発注機関へ技術資料を提出し、その資料をもとに審査が実施されます。
そして、審査を通過した事業者へ指名通知書が送付され、通知書を受け取った事業者だけが競争入札に参加できる仕組みです。
自社の技術力や実績をアピールし、審査を通過することで参加のチャンスが生まれます。
簡易公募型指名競争入札
簡易公募型指名競争入札は、基本的な流れは公募型指名競争入札と同じですが、主に小規模な業務の入札で採用される点が異なります。
発注機関が提示した条件をクリアした事業者のみ、参加の意向を示す書類を提出してエントリーが可能です。
プロジェクトの規模が比較的小さいため、参加者も限定的に選ばれることが多く、入札手続きも簡略化される傾向にあります。
小回りの利く案件を狙う場合に適した方式といえるでしょう。
工事希望型指名競争入札
工事希望型指名競争入札は、他の2種類とは異なり、事業者が自ら参加を希望する仕組みではありません。
この方式では、国や地方公共団体などの発注機関が、特定の条件に基づいて事業者を直接指名します。
そのため、参加するためのハードルは非常に高いといえます。主に、特殊な技術や高度な専門性が求められる工事案件などで採用されるのが特徴です。
豊富な実績と高い技術力を持つ、一握りの事業者だけが参加できる入札です。
指名競争入札の4つのメリット

指名競争入札には、事業者にとって多くのメリットがあります。ここでは、参加することで得られる主な4つのメリットを解説します。
- 落札の確率が向上する
- 官公庁と長期的に良好な関係を築ける
- 価格競争を避けられる
- コストやスケジュールが予想しやすい
これらの利点を理解し、戦略的に活用していきましょう。
落札の確率が向上する
指名競争入札は、落札できる可能性が高い点が大きなメリットです。不特定多数が参加する一般競争入札では、競争が激しくなり、落札の難易度が高まります。
しかし、指名競争入札では、発注機関から指名を受けた限られた事業者のみが参加するため、競争相手が少なくなるのが特徴です。
結果として、相対的に落札の確率が向上します。受注につながりやすい入札案件に集中してリソースを投下できるため、営業活動の生産性も高まるでしょう。
官公庁と長期的に良好な関係を築ける
官公庁との長期的な信頼関係を構築できるのも、指名競争入札のメリットです。この入札で指名を受ける事実は、官公庁から実績や技術力を公式に認められた証となります。
一度指名された事業者は、別の案件でも再び声がかかる可能性が高まり、継続的な受注につながりやすくなるでしょう。
一つひとつの案件で誠実な対応を積み重ねることで、官公庁との間に強固な信頼関係が生まれ、安定した事業基盤を築くきっかけになります。
価格競争を避けられる
指名競争入札では、過度な価格競争に陥りにくいという利点があります。
一般競争入札の場合、最も低い価格を提示した事業者が落札するケースがほとんどのため、利益を度外視した価格競争が起こりがちです。
その点、指名競争入札では参加事業者が限定されているため、極端な価格競争が起こりにくくなります。
これにより、企業の技術力や提案内容が適正に評価され、無理のない価格での受注が期待できるでしょう。
コストやスケジュールが予想しやすい
事業の見通しを立てやすい点も、指名競争入札のメリットです。指名競争入札の案件は、発注機関によって明確な指名基準や事業目的が定められています。
そのため、事業者は案件遂行に必要となるコストやスケジュールを事前に予測しやすく、計画的に準備を進められます。
また、発注機関が求める技術力や品質基準を満たすことが重視されるため、企業の強みを活かした提案がしやすくなるでしょう。
指名競争入札のデメリット

多くのメリットがある一方で、指名競争入札には注意すべきデメリットも存在します。最大のデメリットは、発注機関から指名されなければ、入札に参加する機会すらない点です。
また、一般競争入札に比べて、発注機関が事前にある程度落札候補を想定している場合があり、評価基準が外から見えにくい側面もあります。
特に、新規参入の事業者や設立から年数の浅い事業者は、高い技術力を持っていても、実績不足を理由に指名されにくい傾向があります。
これらのリスクを正しく把握し、対策を講じることが、指名競争入札で成果を出すためには不可欠です。
指名競争入札の流れ【7STEP】

ここでは、公募型指名競争入札を例に、手続きの具体的な流れを7つのステップで解説します。
- 案件の公示:発注機関が、入札案件の概要や参加資格などをWebサイトや公告で公開します。
- 技術資料の提出:参加を希望する事業者は、実績や技術的な提案をまとめた資料を作成し、指定された期日までに提出します。
- 技術資料の審査:発注機関が各社から提出された資料を審査し、指名の条件を満たしているかを確認します。
- 指名通知書の発行:審査を通過した事業者に対し、発注機関から指名通知書が送付されます。
- 入札書の提出:指名された事業者は、指定された仕様に基づいて見積もりを行い、入札書を提出します。
- 開札:定められた日時と場所で入札書が開かれ、落札者が決定されます。
- 契約締結:落札した事業者と発注機関との間で、正式な契約が結ばれます。
公募型指名競争入札の案件を調べる方法

公募型指名競争入札の案件は、官報や電子入札ポータルサイト、各自治体・団体のホームページなどで公示情報を確認できます。
しかし、これらの情報を一つひとつチェックするのは手間がかかります。案件情報の収集を効率化したい場合「NJSS(入札情報速報サービス)」のような専門サービスの活用が有効です。
NJSSを利用すれば、国や地方公共団体、外郭団体などが公開する年間180万件以上の発注情報を一元的に検索できます。
自社に合った案件を素早く見つけ、営業の機会損失を防ぐために役立つでしょう。
指名競争入札を活用するなら株式会社リクロスへご相談ください!

この記事では、指名競争入札の概要から他の入札方法との違いや具体的な種類、メリット・デメリットまでをわかりやすく解説しました。
「入札方法の違いがわからず、失敗できない」「指名競争入札に参加するための条件がわからない」といった課題の解決に繋がったのではないでしょうか。
指名競争入札は、実績と技術力が認められれば、安定した受注につながる魅力的な市場です。
もし、指名競争入札への参加や、自治体への営業活動で不明な点があれば、ぜひ株式会社リクロスへご相談ください。
- URLをコピーしました!