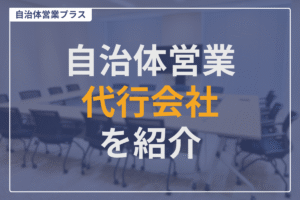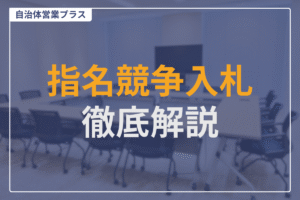一般競争入札とは?自治体での落札方式やメリット・デメリット・入札の流れまで解説
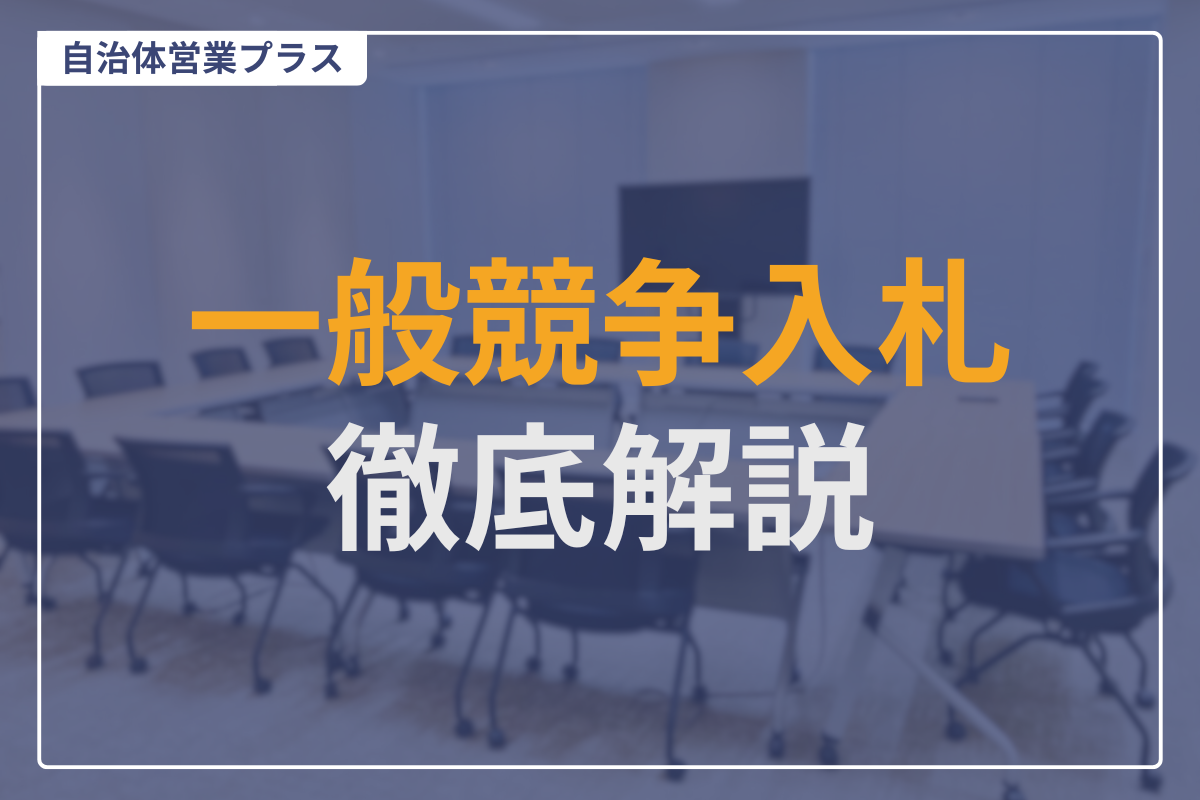
- URLをコピーしました!
「一般競争入札の仕組みがよくわからない」
「初めて参加するけれど、どのような流れで進むのだろうか」
このような疑問を抱えている事業者の方もいるでしょう。一般競争入札は、国や地方自治体の事業に参加し、新たな販路を開拓する大きなチャンスです。しかし、仕組みやルールが複雑そうで、一歩を踏み出せないケースは少なくありません。
この記事では、一般競争入札の基本的な知識から、具体的な参加手順、そして落札確率を上げるためのポイントまで、専門用語を避けながら丁寧に解説します。最後まで読めば、一般競争入札の全体像が明確に分かり、参加に向けた準備を具体的に進められるようになります。
一般競争入札に関するお悩みをお持ちでしたら、ぜひ「自治体営業プラス」にご相談ください。
一般競争入札とは?

一般競争入札とは、官公庁や自治体が発注する事業において、不特定多数の事業者を公募し、最も有利な条件を提示した企業と契約を結ぶ方式です。会計法や地方自治法によって「原則方式」と定められており、公正性・透明性・経済性を確保するために導入されています。
この入札方式では、参加資格を満たしていれば企業規模や実績に関係なく応募できる点が特徴です。そのため、中小企業や新規参入企業にも機会が開かれています。
また、一般競争入札は税金を原資とする公共事業において、住民に対して説明責任を果たすための仕組みです。誰でも参加できる形で入札を実施することで、行政の公正な運営と税金の適正利用を担保しています。
一般競争入札の特徴
一般競争入札は、官公庁を発注者、民間企業を受注者とする契約関係で成立します。入札公告(公示)によって案件情報が広く公開され、参加資格を満たす企業であれば誰でも応募可能です。このように、一般競争入札はオープンで公平な仕組みとして位置づけられています。
入札では、価格のみで落札者を決定する場合と、価格に加えて技術力や提案内容などを総合的に評価する場合があります。これにより、単なる価格競争にとどまらず、質の高い提案を行う企業にもチャンスが与えられます。
透明性と公平性を確保しながら競争原理を働かせることで、税金を適正かつ効率的に使用することができる点が一般競争入札の大きな特徴です。
一般競争入札の落札方式

一般競争入札には主に「最低価格落札方式」と「総合評価落札方式」の2種類の落札方法があります。
最低価格落札方式では、あらかじめ設定された予定価格の範囲内で最も低い価格を提示した事業者が落札します。
この方式は「自動落札方式」とも呼ばれ、物品や役務の調達案件で広く採用されています。ただし、予定価格を下回る場合は落札が認められないため、極端な低価格競争を防ぐ仕組みになっています。
一方、総合評価落札方式では、価格だけでなく技術力や新技術の活用実績、地域貢献度、安全性など複数の要素を総合的に評価して落札者を決定します。
主に建設や工事関連の案件で多く導入されており、価格だけでなく品質や安全性の確保を重視しています。また、評価にあたっては学識者などの外部有識者の意見を取り入れるケースも多く、より公平で客観的な判断が行われます。
一般競争入札の3つのメリット

一般競争入札への参加は、企業にとって多くの利点をもたらします。
- 中小企業や新規参入でも参加できる
- 公平で透明性が高い
- 実績作りのチャンスになる
ここでは、特に注目すべき3つのメリットを解説します。
中小企業や新規参入でも参加できる
一般競争入札は、入札参加資格を取得すれば、企業規模や実績に関係なく応募できます。特別な技術やノウハウを必要としない案件も多く、価格競争を中心に参加できるため、参入のハードルが低いことが特徴です。
また、制限付き一般競争入札の場合でも、一定の要件を満たせば参加できるケースがあります。そのため、中小企業や新規参入企業にとって、新しい販路を開拓し、公共事業へ挑戦するきっかけを得やすい仕組みといえます。
公平で透明性が高い
一般競争入札は、公示や公告によって入札情報が公開されるため、誰でも内容を確認できます。発注者にとっても、入札過程を公開することで説明責任を果たせる合理的な制度です。
また、税金を活用した公共事業である以上、住民に対して公正な運用を示すことが重要です。落札結果や入札金額も公開されるため、透明性が高く、不正や癒着を防ぐ効果があります。
実績作りのチャンスになる
一般競争入札は、実績の少ない企業でも参加できるため、公共事業の経験を積む機会になります。公共案件での実績は、次回以降の入札や民間企業への営業活動において信頼性を高める材料となります。
特に、初期の段階で中小企業が小規模案件を受注し、実績を積み重ねることで、将来的に継続的な契約や大規模案件へのステップアップが可能になります。
一般競争入札の3つのデメリット

多くのメリットがある一方で、一般競争入札には注意すべきデメリットも存在します。
- 価格競争が激しく利益を確保しにくい
- 準備や手続きに手間がかかる
- 技術や提案力が評価されにくい場合もある
参加を検討する際には、以下の3つの点をあらかじめ把握しておくことが重要です。
価格競争が激しく利益を確保しにくい
一般競争入札は多くの企業が参加するため、価格競争に陥りやすい傾向があります。特に「最低価格落札方式」が採用される場合、企業は極限まで価格を下げざるを得ません。
その結果、利益率が低下し、受注しても十分な収益を確保できないケースが多く見られます。短期的な売上確保はできても、長期的な採算性に課題を抱える可能性があります。
準備や手続きに手間がかかる
入札に参加するためには、事前に「入札参加資格」の申請や更新が必要です。これには書類作成や提出など、時間と労力を要します。
さらに、公告内容や仕様書を正確に理解し、不備のない書類を提出しなければなりません。入札価格の設定も慎重に行う必要があり、これらの準備に多くの工数がかかります。落札できなかった場合でも、これまでの準備コストが無駄になるリスクがあります。
技術や提案力が評価されにくい場合もある
一般競争入札では、価格を重視する「最低価格落札方式」が主流のため、企業が持つ技術力や提案内容が十分に評価されないことがあります。
総合評価落札方式の導入が増えてはいるものの、依然として価格優先の傾向が強い現状です。そのため、技術やノウハウで差別化を図る企業にとっては、不利に働く場合があります。
一般競争入札の流れ【7STEP】
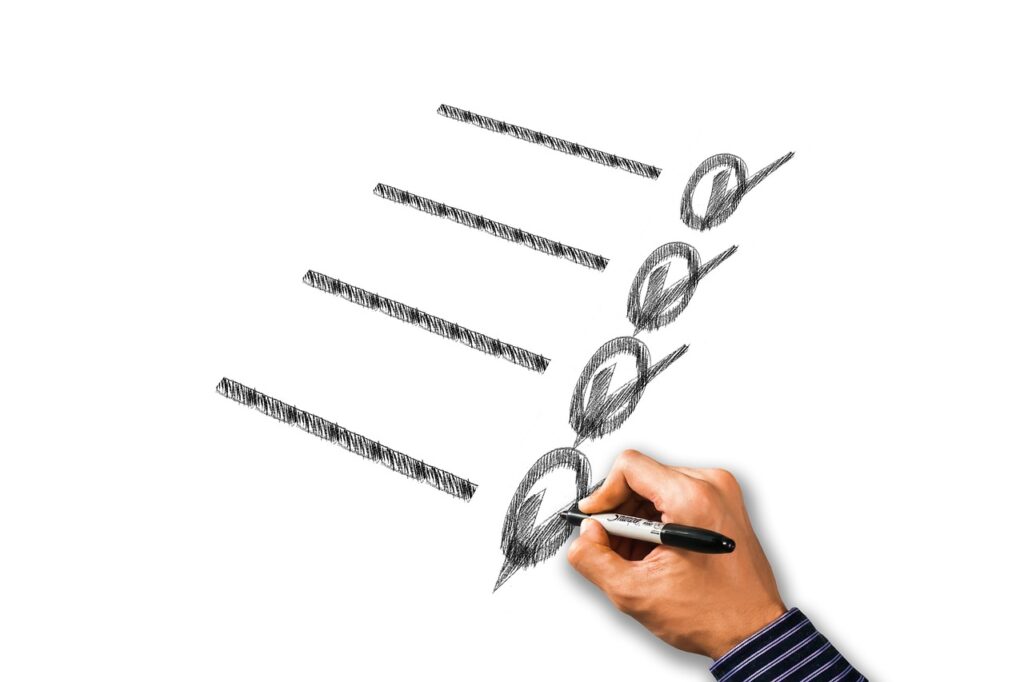
一般競争入札に参加し、契約を締結するまでには、いくつかの決まった段階を踏む必要があります。
- 入札参加資格の取得
- 発注情報を探す(自治体HP・入札情報サービスなど)
- 入札公告・入札説明書の確認
- 入札説明会への参加(必要に応じて)
- 入札手続き(書類提出・電子入札)
- 開札・落札者の決定
- 契約締結
ここでは、そのプロセスを7つのステップに分けて解説します。
1.入札参加資格の取得
一般競争入札に参加するためには、まず「入札参加資格」を取得する必要があります。資格は発注機関や業種ごとに異なるため、複数の自治体や官公庁で入札を行う場合は、それぞれに申請が必要です。
申請には必要書類の提出が求められ、受付期間も機関によって異なります。また、資格は定期的に更新が必要で、更新時期を逃すと入札に参加できなくなるリスクがあります。なお、不正行為の履歴がある事業者は資格を失う可能性があり、入札には参加できません。
入札参加資格についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
関連記事:入札参加資格とは?初心者向けにわかりやすく解説します! | 自治体営業プラス
2.発注情報を探す(自治体HP・入札情報サービスなど)
入札案件は、各自治体や官公庁のホームページに掲載されます。「入札・契約」ページなどで公告が公開されるケースが一般的です。ただし、公示のタイミングは不定期なため、こまめな確認が欠かせません。
また、有料の入札情報サービス(例:NJSSなど)を利用すれば、複数の機関の情報をまとめて検索できるため、効率的に案件を探すことができます。発注予定や仕様検討の段階から情報を把握することで、競合よりも優位に立つことが可能です。
3.入札公告・入札説明書の確認

入札公告は、官報や公報、自治体ホームページ、庁舎掲示板などで公開されます。公告には、「競争対象事項」「資格要件」「契約条件」「入札日時・場所」「入札保証金」など、入札に必要な情報が記載されています。
また、以下のような関連書類も合わせて確認します。
- 入札心得書:基本ルールや遵守事項を記載
- 入札説明書:提出先や手順、納期などを詳細に記載
- 仕様書:業務内容や作業方法を具体的に説明
不明点がある場合は、必ず質問や照会を行い、曖昧な点を残さないようにしましょう。
4.入札説明会への参加(必要に応じて)
案件によっては、入札説明会への参加が必須条件となる場合があります。説明会では、公告や仕様書だけではわからない詳細情報を入手できる貴重な機会です。近年ではオンラインで開催されるケースや、説明会自体を省略する案件も増えています。
ただし、説明会では質問の受付や追加資料の提供が行われることも多いため、可能であれば積極的に参加し、入札条件の理解を深めることが重要です。
5.入札手続き(書類提出・電子入札)
入札手続きには、紙による入札と電子入札の2種類があります。近年は電子入札システムの導入が進み、多くの自治体でオンライン手続きが主流となっています。提出書類に不備があると即失格となるため、複数人でのチェック体制を整えることが重要です。
また、入札価格は過去の落札結果や競合状況を分析した上で慎重に設定します。金額記入や転記ミスを防ぐことが、失格を避けるための基本です。案件によっては入札保証金の提出が求められるため、公告内容を必ず確認しておきましょう。
6.開札・落札者の決定

開札は、定められた日時に実施され、結果は会場または電子システム上で公開されます。開札時には落札者名と落札金額が同時に発表されます。
主な落札方式は次の2つです。
- 最低価格落札方式:予定価格の範囲内で最も低い価格を提示した業者を選定
- 総合評価落札方式:価格に加えて技術力や実績などを総合的に評価して選定
場合によっては、不落(該当なし)や不調(応募なし)となることもあり、その際は再入札や随意契約に切り替えられるケースもあります。
7.契約締結
落札後は、発注機関と正式に契約を締結します。契約内容は入札説明書や仕様書に基づき、納期・支払い条件・検収方法などの詳細が明記されます。契約にあたっては、双方の認識のズレがないよう内容を再確認し、不備があれば速やかに修正・調整を行います。
契約が完了すれば、いよいよ業務開始です。スムーズな履行に向けて、事前準備と内部体制を整えておくことが重要です。
一般競争入札に参加できないケース

一般競争入札は広く門戸が開かれていますが、誰でも無条件に参加できるわけではありません。法律や過去の行いによって、参加が制限される場合があります。
- 法令に基づく参加制限(破産、暴力団関与など)
- 契約違反歴がある場合の参加制限
これらの条件に当てはまらないか、事前によく確認しておく必要があります。
法令に基づく参加制限(破産、暴力団関与など)
地方自治法施行令第167条の4では、契約を結ぶ能力を持っていない者や、破産手続きを開始する決定を受け、まだ復権していない者は参加できないと定められています。
さらに、社会的な公正性を保つ観点から、暴力団員である、あるいは暴力団のような反社会的勢力と関わりを持っている事業者も参加は不可能です。これらの規定は、税金を使って行われる公共の契約において、信頼性と適正さを確保するために設けられています。
契約違反歴がある場合の参加制限
過去に国や自治体との契約において、不正な行為や契約違反を犯したことがある事業者は、一定期間、入札への参加を制限されることがあります。具体的には、故意に工事や製造を雑に行ったり、製品の品質や数量をごまかしたりするなどの不正行為が挙げられます。
また、他の参加者と談合して入札の公正さを妨害した場合や、正当な理由がないのに契約を履行しなかった場合も対象です。こうした行為が発覚すると、その内容に応じて最大で3年間、一般競争入札に参加できなくなるペナルティが科されることがあります。
一般競争入札で落札するための3つのポイント

一般競争入札で落札を勝ち取るためには、単に参加するだけでなく、戦略的なアプローチが求められます。
- 自社に合った案件を選ぶ
- 発注元・競合の傾向を分析する
- 仕様書・入札説明書を徹底的に読み込む
ここでは、落札の確率を高めるために押さえておきたい3つの重要なポイントを紹介します。
自社に合った案件を選ぶ
一般競争入札では、大企業や実績のある企業が必ずしも有利とは限りません。重要なのは、自社が確実に対応できる規模や範囲の案件を選ぶことです。自社の人員・設備・スケジュールを踏まえたうえで、無理のない範囲で入札に参加することで、実行力を評価されやすくなります。
また、競争倍率が高い案件は落札の難易度が上がるため、あえて競争が少ない案件を狙うのも有効です。普段から過去の落札金額や競合企業の実績を分析し、「どのような案件なら勝てるか」を見極める習慣を持つことが大切です。
発注元・競合の傾向を分析する
案件選びと並行して、発注元である自治体や競合他社の動向を分析することも不可欠です。過去の入札結果を調査すれば、競合となる企業がどのくらいの価格で落札しているのか、その傾向を把握できます。
また、自治体が公表している行政計画や予算書を確認すると、今後どのような事業に力を入れようとしているのか、発注のニーズを予測する手がかりになります。発注元の方針や、どのような点を評価基準として重視しているのかを深く分析し、自社が有利に戦える条件を探しましょう。注目度の低い案件をあえて狙うなど、戦略的な視点を持つことが落札につながります。
仕様書・入札説明書を徹底的に読み込む
最も基本的でありながら、最も重要なのが、公開される書類を徹底的に読み込むことです。入札に関する納期、提出先、必要な書類といった重要事項は、すべて入札説明書や仕様書に記載されています。
これらの書類に記載されたルールを守れない場合、例えば提出書類に一つでも不備があれば、その時点で失格となってしまいます。公告が出たらできるだけ早く内容を確認し、少しでも不明な点や疑問があれば、必ず期間内に発注機関へ質問してください。当たり前の確認作業を怠らず、不備をゼロにすることを徹底する姿勢が重要です。
一般競争入札に関するお悩みなら「自治体営業プラス」にご相談ください

一般競争入札は、官公庁や自治体の発注に広く参加できる仕組みであり、中小企業や新規参入企業でも十分にチャンスがあります。仕組みやルールを正しく理解し、入札資格の取得や公告内容の確認など、基本的な準備を丁寧に進めることで落札の可能性を高められます。
案件の選定、書類作成、入札価格の設定などを計画的に進めつつ、過去の落札データや発注元の傾向を分析しましょう。競争倍率の低い案件を狙う、仕様書を細部まで読み込むといった工夫も有効です。
正しい知識と戦略をもって行動すれば、初めてでも一般競争入札で成果を上げることは十分に可能です。自社に合った案件を見極め、少しずつ実績を積み上げていきましょう。
入札に関して分からないことや、より具体的なサポートが必要な場合は、ぜひ「自治体営業プラス」にご相談ください。専門のコンサルタントが、皆さまの自治体営業を力強くサポートします。
- URLをコピーしました!