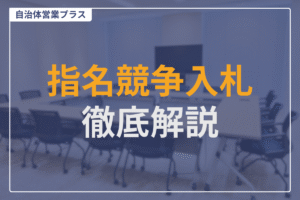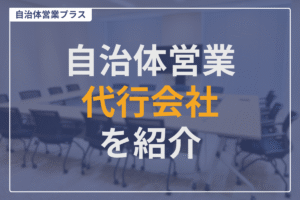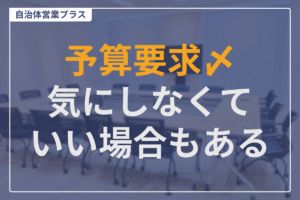対面営業の使いどころの判断基準は?自治体ビジネス支援会社が解説

- URLをコピーしました!
はじめに
 木藤昭久
木藤昭久こんにちは!リクロスの木藤です。
今回は、対面営業の使いどころの判断基準について書いていきます。
コロナ禍によりほぼ全ての自治体がZoomでのオンライン会議に対応できるようになりました。
法人営業と同様、今となっては「オンライン会議は失礼」みたいなイメージは減ってきている印象です。
しかし、同じ商談であれば対面の方が温度感が上がりやすいのは間違いないところ。
自治体ビジネスは全国が対象の企業様もいるので、本記事が少しでも参考になれば幸いです。
それでは見ていきましょう!
対面営業の使いどころの判断事例
最初から全て
全国に営業拠点があったり、参入初期に顧客の声を聞くために意識的に対面営業される企業様がいらっしゃいます。
上述のとおり対面営業は非常に有効ですので、お金や時間の兼ね合いも踏まえて実施されているようです。
人口規模
「都道府県や政令指定都市であれば必ず対面」という企業様もいます。
人口規模や職員数に応じて価格が上昇するサービスであれば、受注単価が高くなるので、人口規模を見て対面商談を判断するのは良い考えだと思います。
距離
「本社が東京なので関東であれば訪問する」などです。
他にも「新幹線で通える人口20万人以上の地域」といった基準で動いている企業様もいます。
温度感
初回のオンライン商談で温度感が高ければ次回は対面で訪問する企業様もいます。
ある企業様は「せっかく伺うので、よろしければ意思決定の関係者様にできるだけお集まりいただけますでしょうか?」と打診しているようでして、「これはいいな」と唸りました。
デモ
デモを依頼された場合に訪問を活用される企業様もいます。
対面でしかデモができなければもちろん訪問するのですが、中には「オンラインでもデモはできるが訪問する」というところも。温度感を上げるための意思決定ですね。
ついで
他の予定のついでに訪問するパターンです。
自治体同士の距離感があるものの、できるだけ1日3件はアポを入れたいところですね。
最後に
対面営業の使いどころの判断基準について書きました。
特に地方の自治体からすると「わざわざ遠くから来てくれたんだ」と思ってもらいやすいので、自治体ビジネスにおいて対面営業の有効性は高いでしょう。
本記事が少しでもお力になれば幸いです。
- URLをコピーしました!