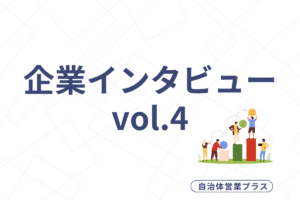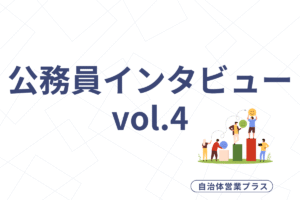【特別インタビューvol.1】入札情報サービスLabidについていろいろ伺いました!

- URLをコピーしました!
はじめに
 木藤昭久
木藤昭久こんにちは!リクロスの木藤です。
今回は、公共営業の生産性を向上させるAI入札情報サービスLabidを提供するNehan株式会社様にインタビューのお時間をいただきました。
自治体営業において、入札情報サービスが必須な企業様も多いかと思います。
これまでは「情報が集まっている」にいう価値にとどまっていた入札情報サービスですが、Labidは上述の通り「公共営業の生産性を向上させる」という点がいちばんのポイントだと認識しています。
本記事が少しでも皆様の参考になればと思います。
それでは見ていきましょう!
インタビュー
Labidに関する概要
木藤:今回はお時間をいただきありがとうございます!まずはLabidについてざっくり教えていただけますでしょうか。
ひとことで言うと、公共営業の生産性を向上させるAI入札情報サービスです。入札・落札情報の収集や通知という一般的な機能に加え、AIによる提案書のひな型作成、案件進捗のボード管理までを一気通貫でサポートできます。
木藤:画面を見せてもらいましたが、デザインも優れていて良いですね。自治体営業に限らないですが営業組織はExcelが乱立したりしがちなので、営業支援プラットフォームのような形になっているのが素晴らしいです。
まさにそういった方向性を目指していて、公共営業を支援するために今後もどんどん必要な機能をアップデートしていこうと考えています。
木藤:Labidは案件管理もできるんですね。
そうですね。民間営業の現場では営業支援ツールが普及していますが、自治体営業ではまだその仕組みが整っていません。Labidは公共営業に特化した営業支援プラットフォームのような立ち位置を意識しています。
木藤:Excelやメールで分散管理している企業が多いので、それを一元化できるだけでも価値が大きいですね。
公共調達市場は中小企業でも勝負できる
木藤:公共調達の市場についてもお聞かせください。実際どれくらいの規模感があるのでしょうか?
国や自治体、独立行政法人を合わせると約26兆円規模の市場と言われています。その中心はやはり地方自治体で、入札やプロポーザルが日々どんどん公示されていますね。しかも資格保有者の84%は中小企業なので、中小でも十分に勝負できる領域だと考えています。
木藤:当社の支援先も基本的には中小企業なので、私も自信を持って「中小企業でもいけます」と言えますね。
公共領域は世間的なイメージよりハードルが低い
民間は様々な施策を打ってアポ獲得から狙っていきますが、公共領域は案件情報が公開されているので、ハードルが低いんですよね。世間的には「自治体営業は難しい」など言われますが…。
入札書類が複雑そう、参加資格の条件が厳しそう、情報が分散していて探しにくいという印象から、まだ一歩を踏み出せていない企業も少なくありません。
しかし実際には、自治体・官公庁案件のリード獲得は民間営業よりもコスト効率が高いと考えています。
木藤:たしかにそうですよね。自治体はアポ獲得のハードルも低めで、やり方さえ正しければアポ率5~10%は行く印象です。民間ビジネスと比べてアプローチ手法も限られているので、実際はそんなに頭抱えるほどは難しくないです。
まず実績を作るのが大事
木藤:入札で成果を出す企業に共通するパターンとかはありますか?
短期で諦めない点です。入札やプロポーザルに参加して受注できる確率は10~20%くらいなので、最低でも半年単位でのPDCAは必要ですね。実際にLabidを使っているお客様が、3年間同じ事業者に決まっていた自治体からプロポーザルで受注したこともあります。
木藤:プロポーザルでひっくり返ることは、世間的なイメージよりは多い印象です。わりといけますよね。
あとは、最初の受注は採算度外視という企業様はけっこういらっしゃいます。
木藤:自治体ビジネスは流れに乗ったら実績が実績を呼びますが、最初は簡単じゃないんですよね。「1,2自治体から受注すればOK」というスタンスでは財務面で損になると思うので、長期的に受注数を増やしていっていただきたいです。
数を打つためにも、入札情報サービスで案件をどんどん見つけてほしいと思います。
木藤:数は大事ですよね。質を上げるつもりで取り組んでほしいとは思いますが、営業活動である以上確率論からは離れられないです。
導入はスタッフを一人増やす感覚で
木藤:現場からすると「人を一人増やすような感覚で使える」というのも魅力だと思います。参入初期にいきなり人を増やすのもいいですが、入札情報サービスの活用は漏れなく検討してほしいですね。
そうですね。入札情報を収集・整理し、期日や進捗を管理するのを人手でやろうとすると工数が膨大になります。Labidを導入すればその役割をシステムに任せられるので、スタッフを一人採用する感覚で導入する企業様が多いです。
AIで書類チェックや提案書作成が楽に
木藤:公募要領や仕様書のチェックが楽になる機能もあるんですね。
AIサマリという機能としてあります。1件の案件情報だけで関連資料が何十ページになることも珍しくないですし、資料が複数に分かれているので生成AIに投げるのも手間なんですよね。
木藤:AIで提案書のベースまで作れるのもおもしろいです。
そうなんです。公示書類をもとに提案書の骨子を自動で生成できます。
木藤:自治体のプロポーザル審査では、Q&AのAが抜けているとその項目は採点できず、その項目が0点扱いに近づくリスクがあります。企画提案書に書いていないことを審査側が勝手に高く評価すると、不正に見えてしまうんですよね。だからこそ漏れをなくすのは非常に重要で、その点でLabidの自動生成は助けになりそうです。
最後に
木藤:今日はありがとうございました。最後に何かメッセージがあればお願いします。
私たちは「公共調達を、もっと開かれたものにする」ことを目指しています。
その実現のために、Labidを通じて公共営業のあり方そのものをアップデートしていきます。
▽無料トライアルご希望の方はこちら
- URLをコピーしました!