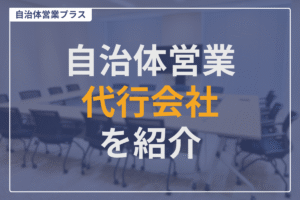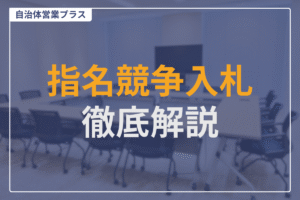自治体入札とは?仕組みや種類・流れ・落札方式まで解説【初心者必見】
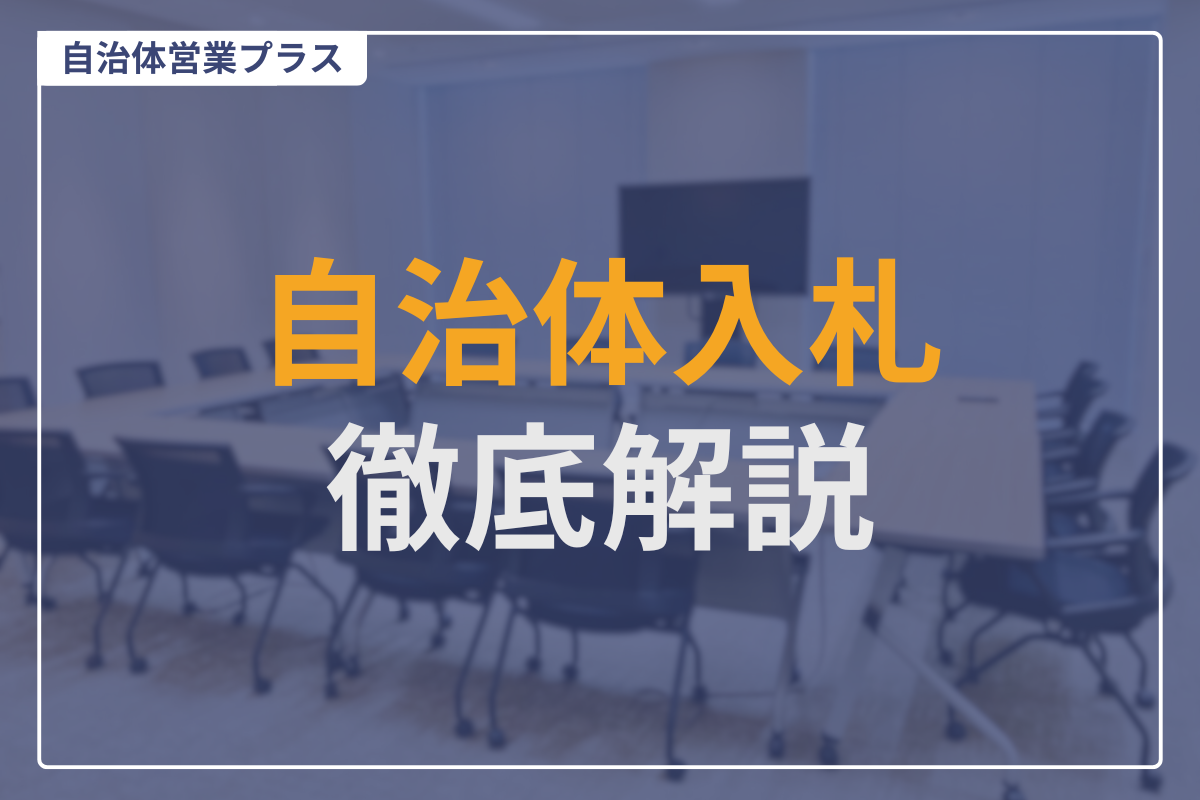
- URLをコピーしました!
「自治体入札の仕組みが複雑でよくわからない」
「自社がどの入札方式で参加できるのか知りたい」
このような悩みをお持ちではありませんか。
自治体入札は、公平性や透明性が求められるため、特有のルールや流れが存在します。仕組みを正しく理解しないまま参加しようとすると、準備に時間がかかったり、機会を逃してしまったりするかもしれません。
この記事では、自治体入札の基本的な仕組みから、対象となる分野、入札や落札方式の種類、参加するための具体的な流れ、そして初心者が押さえておくべきポイントまで、網羅的に解説します。最後まで読めば、自治体入札の全体像がわかり、参加に向けた第一歩を自信をもって踏み出せます。
また、自治体入札に関する具体的なサポートを受けたい方は、ぜひ「自治体営業プラス」にご相談ください。
自治体入札とは?

自治体入札とは、国や地方自治体といった公的機関が、民間企業へ業務を委託したり、物品を購入したりする際に用いる契約方式のことです。
一般的に「公共入札」とも呼ばれます。入札の財源は税金であるため、契約のプロセスには公平性、透明性、そして将来にわたる公正さが強く求められます。そのため、どのような業務が、どのくらいの金額で、どの企業に発注されたのかといった入札情報や落札結果は、原則としてすべて公開されなければなりません。
また、公正な競争を妨げる入札談合は、刑法や独占禁止法によって厳しく禁止されています。違反した場合は、懲役や罰金などの重い罰則が科されるため、法令を遵守した対応が不可欠です。
自治体入札が行われる主な分野

自治体入札は、非常に幅広い分野で実施されています。
- 物品調達
- 役務提供
- 建設工事
- 測量
- コンサルティング
ここでは、主な5つの分野を紹介します。
物品調達
庁舎で使われる机や椅子、パソコン、事務用品などの購入が、物品調達の対象です。ほかにも、学校で使われる教育用の設備や、公立病院で必要な医療機器なども、自治体入札によって調達される場合があります。
調達金額や案件の条件によっては「全省庁統一資格」という、国の機関への物品提供などに必要な資格の取得が求められることもあります。案件は公告され、条件を満たせばどの企業でも参加可能です。
役務提供
役務提供とは、清掃、警備、運搬といった、自治体の業務を支える各種サービスを提供する業務です。例えば、学校給食の調理業務や、庁舎の設備を管理するビルメンテナンス業務なども役務提供に含まれます。
サービスの品質を安定して提供できるかという点から、企業の過去の実績が評価の対象となるケースも少なくありません。また、労務費の適切な転嫁への対応が入札時に求められることもあります。
建設工事
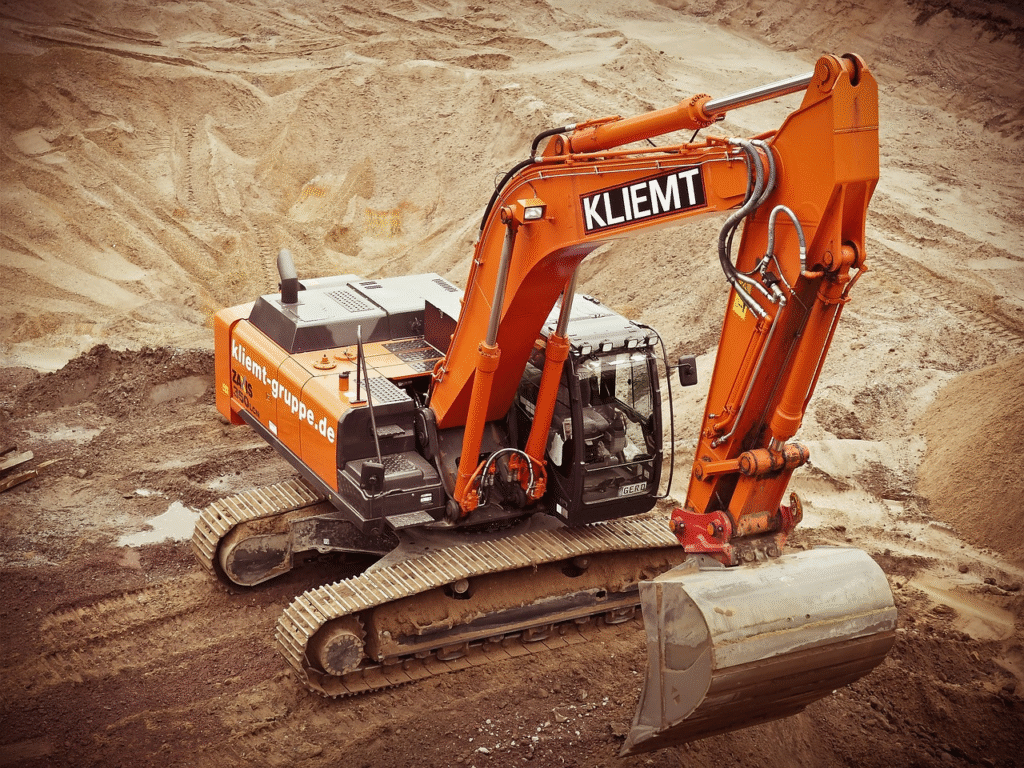
道路や橋、公共施設の新設や改修、修繕などが建設工事の対象です。災害からの復旧工事など、緊急を要する案件も多く、社会インフラを維持する上で欠かせない分野といえます。
公共工事では、構造物の品質を確保することが極めて重要になるため、価格だけでなく技術力も評価する「総合評価落札方式」や、低価格での入札を制限する制度が導入されることが多くあります。
測量
測量は、主に建設工事の前段階で必要となる専門業務です。測量によって得られた正確なデータは、都市計画を策定したり、新しい道路を設計したりするための、基礎資料として活用されます。
入札に参加するための資格は「測量・建設コンサルタント等」に区分されており、専用の様式が存在します。過去の実績や測量の精度が落札の結果に影響を与えやすい分野です。
コンサルティング
コンサルティング分野では、公共事業に関する建設コンサルタント業務が中心です。業務内容は、施設の設計や工事の監理、専門的な技術提案などです。
近年では、情報システム開発やイベント企画、自治体の広報戦略立案といった多様な業務も入札対象となる場合があります。価格だけでなく企画内容が重視されるため、企画提案型の「プロポーザル方式」が多く採用される傾向にあります。
自治体入札の種類

自治体入札には、いくつかの種類があり、案件の性質や目的によって使い分けられています。主な入札の種類は、下記のとおりです。
- 一般競争入札
- 指名競争入札
- 随意契約
- WTO対象入札
ここでは、それぞれの方式について詳しく解説します。
一般競争入札|誰でも参加できる基本方式
一般競争入札は、自治体が定める参加資格を満たしていれば、どの企業でも参加できる最も標準的な入札方式です。
多くの企業が参加できるため、公平性と透明性を確保しやすく、大部分の入札がこの方式で実施されています。新規参入を目指す企業や、これから実績を積みたい企業に向いている方式といえるでしょう。
ただし、競争が激しくなるため、価格競争に陥り利益を確保しにくい場合があります。
指名競争入札|実績ある企業のみが呼ばれる方式
指名競争入札は、発注者である自治体が、過去の実績や信頼性などを基準に特定の複数の企業を指名し、その企業間だけで競争させる方式です。
参加できる企業が限られるため、落札できる可能性が一般競争入札よりも高くなります。一方で、公平性や透明性の観点から、この方式が採用される案件は減少傾向にあります。近年では、参加を希望する企業を募る「希望制指名競争入札」という仕組みも増えています。
随意契約|入札を行わず直接契約する方式
随意契約は、競争入札を実施せず、発注者が特定の事業者を選んで直接契約を結ぶ方式です。
地方自治法施行令で適用できる条件が厳しく定められており、例外的な方式と位置づけられています。特定の事業者しか持たない高い技術力が必要な場合や、契約の性質が競争入札に適さない場合に用いられます。
透明性が低いため原則として抑制される方式ですが、「企画競争入札(プロポーザル方式)」など多様な形態があります。
随意契約についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もご確認ください。
関連記事:【徹底解説】随意契約とは?自治体&自治体営業経験者が解説します! | 自治体営業プラス
WTO対象入札|国際案件に適用される入札
WTO対象入札とは、WTO(世界貿易機関)の政府調達協定に基づき、国籍を問わず参加機会を設ける入札のことです。
国や自治体が調達する物品やサービスで、定められた基準額を超える契約が対象となり、外国企業も日本の企業と同じ条件で参加できます。国際的な競争にさらされているため、規模の大きな案件が中心です。この入札を実施できるのは、都道府県や指定都市などに限られています。
自治体入札で落札者を決める方式の種類
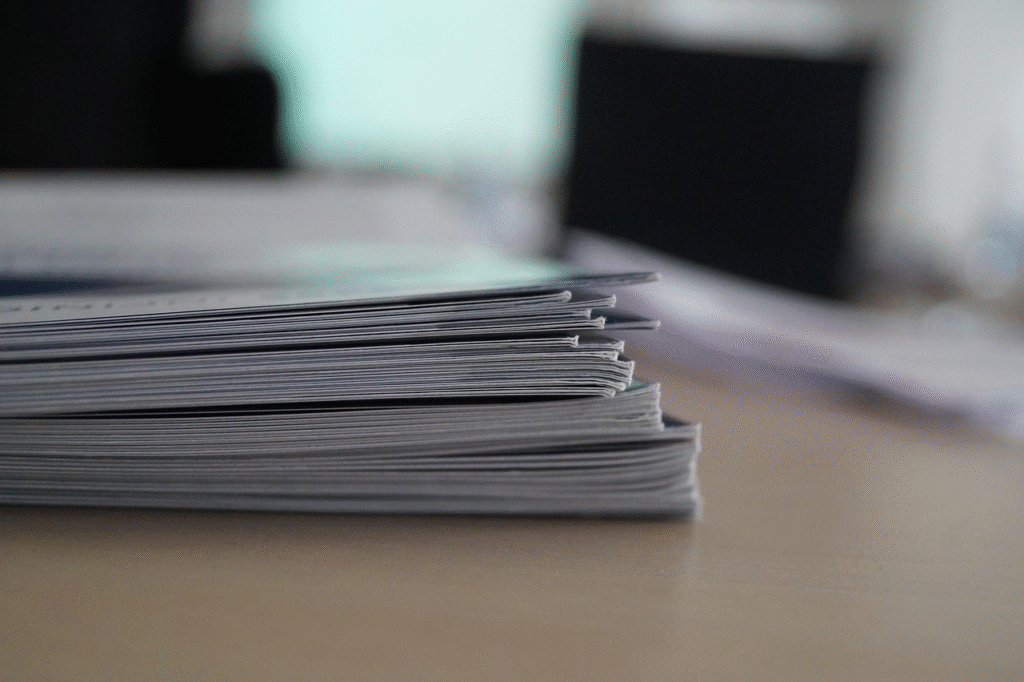
入札に参加した企業の中から、実際に契約する相手(落札者)を決定する方法にも、次のような種類があります。
- 最低価格落札方式
- 最低制限価格制度
- 低入札価格調査制度
- 総合評価落札方式
- プロポーザル方式
ここでは、代表的な5つの方式を紹介します。
最低価格落札方式
提示された入札価格が、最も低い事業者を落札者とする、非常にシンプルな方式です。
価格のみで落札者が決まるため公平性が高い一方で、受注したいがために企業が必要以上に低い価格で入札する「ダンピング」が起きる可能性があります。ダンピング受注は、サービスの品質低下や、労働者へのしわ寄せにつながる恐れがあるため、後述する最低制限価格制度などと併用されることが多くあります。
最低制限価格制度
発注者である自治体が、契約内容の品質を担保するために、あらかじめ入札価格の下限となる「最低制限価格」を設定する制度です。
入札時に提示された価格が、設定された最低制限価格を下回った場合、その入札は失格となります。ダンピングを防ぐ目的で運用されており、公共工事や物品の調達など、幅広い案件で適用されています。
低入札価格調査制度

入札価格が極端に低いと判断された場合に、発注者がその価格で契約をきちんと履行できるか調査し、落札の可否を判断する制度です。
調査対象となった事業者は、見積もりの内訳や履行体制、過去の実績などをまとめた資料を提出し、審査を受けます。審査の結果、適正と認められれば落札できますが、不適正と判断された場合は失格となり、次に低い価格を提示した事業者に権利が移ります。
総合評価落札方式
価格だけでなく、事業者が持つ技術力や実績、安全性への取り組み、提案内容といった複数の項目を点数化し、合計点が最も高い事業者を落札者とする方式です。
学識経験者など外部の専門家が評価に加わることで、選定プロセスの透明性を高めているケースもあります。単なる価格競争に陥らず、事業の品質や企画力を重視できる点が大きな特徴です。
プロポーザル方式
価格を評価の対象とせず、提出された企画提案書やプレゼンテーションの内容だけで契約相手を決定する方式です。
そのため、事業者の企画力や創造性、専門性が最も重視されます。設計業務やコンサルティング業務、システムの開発、イベントの運営といった、専門的なノウハウが必要な案件で多く用いられています。コンペ形式で選定する「企画競争入札」も、この方式の一種です。
プロポーザル方式についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もご確認ください。
関連記事:【自治体営業】入札とプロポーザルの違いとは?営業ノウハウも解説! | 自治体営業プラス
自治体入札の流れ【6STEP】

自治体入札に参加し、契約を獲得するまでには、いくつかの決まった手順を踏む必要があります。
- 入札参加資格を取得
- 入札情報を確認
- 仕様書を確認し説明会に参加
- 入札
- 開札・落札の決定
- 契約締結、業務開始
ここでは、その流れを6つのステップにわけて解説します。
1.入札参加資格を取得
自治体入札に参加するには、まず「入札参加資格」を取得しましょう。
この資格は自治体ごとに申請が必要で、建設工事、物品調達、役務提供といった分野ごとに登録が分かれています。資格申請の際には、登記事項証明書や納税証明書、財務諸表といった書類の提出が求められます。
資格の有効期限は1年から3年程度で、期限が切れる前に更新手続きをしなければなりません。
入札参加資格についてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご確認ください。
関連記事:入札参加資格とは?初心者向けにわかりやすく解説します! | 自治体営業プラス
2.入札情報を確認
入札参加資格を取得したら、次に入札案件の情報を探しましょう。
案件の情報は、各自治体のウェブサイトや、民間の入札情報サービスなどで公開されています。一般競争入札の情報は公告として公開され、全企業が閲覧可能です。案件の公告には、入札方式や契約の予定価格、詳しいスケジュールなどが明記されています。
入札期日の10日前までに公告されることが一般的です。
3.仕様書を確認し説明会に参加

興味のある案件を見つけたら、業務の詳しい内容が記載された「仕様書」を入手して確認しましょう。
仕様書には、業務の範囲や納期、満たすべき条件など、入札金額を見積もるために不可欠な情報がすべて記載されています。案件によっては、仕様書を受けとるために説明会への参加が必須の場合もあります。
説明会では、仕様の変更点や補足情報が伝えられることもあるため、必ず参加して最新情報を把握してください。
4.入札
仕様書の内容を十分に理解し、見積もりを算出したら、期日までに入札します。主な入札方法は以下の3種類です。
- 会場入札:指定された会場で一斉に入札を実施する方式
- 電子入札:ICカードや電子証明書を使用して、専用のシステムから入札する方式
- 郵便入札:指定された期日までに、入札書を郵送する方式
近年は透明性や業務の省力化の観点から電子入札が普及しています。書類の不備や提出忘れは失格に直結するため、時間に余裕を持って対応してください。
5.開札・落札の決定
入札が締め切られると、開札が行われ、各企業の入札内容が公開されます。その後、最低価格落札方式や総合評価方式といった、あらかじめ定められた方法に基づいて落札者が決定されます。
最低制限価格制度などにより、過度に安い価格での入札は失格となる場合があるため注意しましょう。落札の結果は、自治体のウェブサイトなどで公開され、市民に対する透明性が確保されます。
6.契約締結、業務開始
落札者に決定したら、契約書を作成し、双方で押印して契約を正式に締結させましょう。契約書には、業務の具体的な内容、納期、金額、報告義務などが明記されます。
契約締結後に業務が開始となり、実務に入る前に自治体の担当者と打ち合わせを行うケースが多いです。業務終了後には、報告書の提出などが求められる場合もあります。
初めて自治体入札に挑戦する際の4つのポイント

初めて自治体入札に参加する企業が、成功の確率を高めるためには、いくつか押さえておくべきポイントがあります。
- 全省庁統一資格を早めに取得する
- 入札情報サービス(NJSSなど)を活用する
- 部署横断で情報収集・準備を進める
- 過去の落札結果を調べて戦略を立てる
これらのポイントを意識して、周到な準備を行いましょう。
全省庁統一資格を早めに取得する
全省庁統一資格は、「物品の製造・販売」や「役務の提供」などの分野で、国の機関の入札に参加するために必須の資格です。
取得には登記事項証明書や納税証明書などの提出が必要で、審査には数週間から数ヶ月かかる場合があります。資格取得が遅れると、参加したい案件の機会を逃してしまうため、事業計画に合わせて早めに準備を進めることが重要です。
一度取得すれば1〜3年間有効ですが、更新手続きが必要な点にも注意してください。
入札情報サービス(NJSSなど)を活用する
全国の自治体が入札情報をそれぞれのウェブサイトで公開しているため、自社に合う案件を効率的に探すのは簡単ではありません。
民間の入札情報サービスを利用すると、全国の入札情報を一括で検索でき、案件探しの手間を大幅に削減できます。NJSSのようなサービスでは、落札情報や競合企業の動向も調べられます。過去の落札結果から相場感を把握し、戦略を立てる上でも役立ちます。
部署横断で情報収集・準備を進める
入札案件は、提出書類や資格条件が多岐にわたるため、一つの部署だけで対応するのは難しい場合があります。
営業部門、技術部門、法務部門など、社内の関連部署が連携して情報収集や準備を進める体制を整えましょう。他部署を巻き込むことで、人的リソースを増やし、情報収集のスピードと精度が向上します。また、全社で取り組むことで、社内にノウハウが蓄積され、次回以降の入札に活かせます。
過去の落札結果を調べて戦略を立てる
過去の落札金額や落札企業の情報は、各自治体のウェブサイトや入札情報サービスで公開されています。これらの情報を分析し、競合企業の入札価格の傾向を把握することで、過度な低価格での入札や赤字リスクを避けられます。
また、自治体ごとの案件の傾向(継続的な発注が多いか、一度限りの発注かなど)を把握しておくことも、戦略を立てる上で有利に働きます。
自治体入札に関するお悩みなら「自治体営業プラス」にご相談ください

自治体入札は、仕組みや流れを正しく理解することで、企業規模に関わらず大きなビジネスチャンスをつかむことができます。入札参加資格の取得や情報収集、仕様書の確認などを計画的に進め、全省庁統一資格や入札情報サービスを活用することで、参加のハードルを下げることが可能です。
また、過去の落札データを分析し、自社の強みを生かした提案を行うことで、落札の可能性を高められます。自治体との取引は長期的な信頼関係構築にもつながるため、正確な手続きと誠実な対応を心がけましょう。
初めて自治体入札に挑戦する際は、専門知識や実務ノウハウを持つ支援サービスを活用するのもおすすめです。
自治体入札に関する具体的なサポートを受けたい、あるいは自社に合った案件を見つけるためのアドバイスがほしいとお考えの方は、ぜひ「自治体営業プラス」にご相談ください。
- URLをコピーしました!