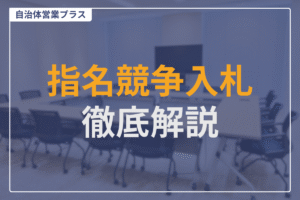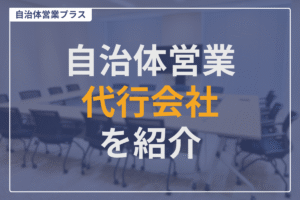プロポーザル方式とは?自治体が利用する流れと2つのメリットを解説
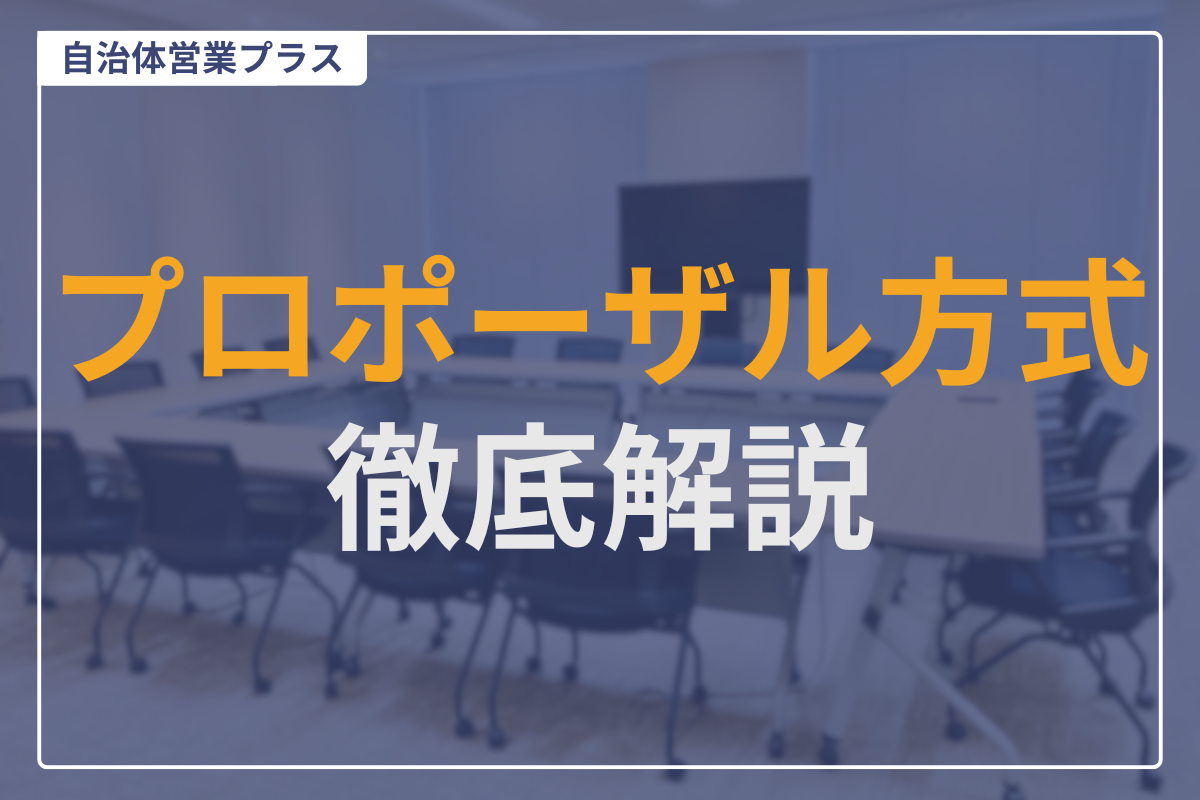
- URLをコピーしました!
「プロポーザルの仕組みは複雑で、理解が追いつかない」
「制度を導入する際の、内部や議会での調整が不安だ」
この記事を読んでいる方のなかには、このような悩みをおもちではないでしょうか。
プロポーザル方式は、価格だけでなく、事業者の提案内容を総合的に評価して契約相手を決めるための仕組みです。
専門的な知識や技術が求められる事業で、優れた事業者を選ぶ際に役立ちます。この方式を深く理解し、流れに沿って手続きを進めれば、住民サービスの向上につながる事業を滞りなく実現可能です。
本記事では、プロポーザル方式の基本的な知識から、自治体が実際に利用する際の流れを7つのステップで詳しく解説します。
あわせて、企画競争入札の主な種類や、自治体がプロポーザル方式を導入するメリット・デメリットも紹介しました。
この記事を最後まで読めば、プロポーザル方式への理解が深まり、自信をもって手続きを進められるようになります。
指名競争入札に関して、さらに詳しい情報が必要な場合は株式会社リクロスの資料もあわせてご活用ください。
プロポーザル方式とは?

プロポーザル方式とは、地方自治体などが事業を委託する企業を選ぶための方法のひとつです。複数の事業者から事業に関する提案を受け、その中から最も優れた内容を提案した事業者を選びます。
価格の安さだけで決める競争入札とは異なり、提案の質や独創性、事業者の実行能力などを総合的に評価するのが大きな特徴です。
そのため、専門的な知識や技術力が求められる事業や、新しいアイデアが必要な事業で採用される場合があります。
この方式により、自治体は自身の課題解決に最も貢献してくれるパートナーを見つけやすくなります。
自治体がプロポーザル方式を利用する流れ【7STEP】

自治体がプロポーザル方式で事業者を選ぶには、いくつもの手順を踏む必要があります。ここでは、具体的な流れを7つのステップにわけて解説します。
- 参加資格の条件を定める
- プロポーザルの実施を公告する
- 参加表明の募集と確認をする
- 提案内容の受け付けと選定をする
- 選定者に通知をする
- 質疑応答でヒアリングをする
- 契約先を決定し契約締結をする
それぞれのステップの目的をしっかり理解し、手続きを円滑に進めましょう。あわせて、提案書を選定する際に確認すべきポイントも紹介します。
STEP1:参加資格の条件を定める
はじめに、発注者である自治体は、どのような事業者に参加してほしいかを考え、参加資格の条件を決めます。
事業内容にあわせて、過去の実績や専門的な資格、所在地の要件などを設定するのが一般的です。
同時に、提案内容を評価するための基準も作成する必要があります。評価基準を明確にしておかないと、どの事業者が最適なのかを公平に判断できません。
評価項目や配点を具体的に定め、透明性の高い選定を目指す必要があります。この段階でしっかりとした土台を築くことが、後の工程をスムーズに進めるための鍵となります。
STEP2:プロポーザルの実施を公告する
参加資格や評価基準が固まったら、自治体のウェブサイトなどでプロポーザルの実施を正式に知らせます。この公告には、事業の目的や内容、参加資格、スケジュールなどの詳細な情報を含める必要があります。
案件の規模や専門性によっては、ウェブサイトでの案内に加えて、事業者向けの説明会を開催するのもひとつの手です。
説明会を開くことで、事業者からの質問に直接答えられ、事業への理解を深めてもらうきっかけになります。
より多くの質の高い事業者からの参加を促すために、情報の伝達方法を工夫することも重要です。
STEP3:参加表明の募集と確認をする

公告をみて関心をもった事業者から、参加の意思を示す「参加表明書」を提出してもらいます。
提出された書類をもとに、事業者がSTEP1で定めた参加資格を満たしているかを確認する作業です。
資格があると認められた事業者には、次のステップである提案書の提出を依頼します。この段階で、参加を希望する事業者の数や顔ぶれがある程度わかるため、今後の審査スケジュールを具体的に調整する上でも重要なステップです。
資格確認は、後の選定作業を円滑に進めるための大切な準備といえます。
STEP4:提案内容の受け付けと選定をする
参加資格をもつ事業者から提出された提案書を受け付け、審査を開始します。
事前に作成した評価基準に沿って、企画の内容や事業の実施体制、事業者の能力などを多角的に評価する工程です。
この書類審査を通じて、特に優れた提案をした事業者を3社から5社程度に絞り込み、次の選考段階へと進めるのが一般的です。
ここでの評価が、最終的な契約相手を決めるための土台となります。提案書を審査する際は、いくつかの重要な点を確認する必要があるため、次の項目で詳しく見ていきましょう。
十分な資金があるかチェック
提案書を審査する上で、事業者に十分な資金があるかの確認は欠かせません。
公共事業の費用は最終的に自治体が支払いますが、事業が完了するまでは事業者自身の資金でやりくりする必要があるからです。潤沢な自己資金がある事業者の方が、業務の遂行にも余裕が生まれます。
金融機関からの融資を活用して参加する事業者もいますが、資金繰りに余裕があるかどうかは、事業を安定して継続できるかの一つの指標です。
万が一の事態にも対応できる財務的な体力があるか、慎重に見極める必要があります。
遂行できる能力があるかチェック
事業を最後までやり遂げる能力が事業者にあるか、厳しく見極める必要があります。
住民の大切な税金を投入する公共事業は、決して失敗が許されないからです。具体的には、事業を担当する従業員の数や、従業員がもつ専門的な能力、国家資格などの保有状況を確認します。
あわせて、過去に類似の事業を手がけた実績があるかも重要な判断材料です。これらの情報から、事業者が業務を確実に遂行できる組織力と技術力を備えているかを総合的に判断します。
目的を理解できているかチェック
事業者が、自治体が事業を行う目的を正しく理解しているか、という点も提案書で見るべきポイントのひとつです。自治体の事業は年度単位で計画されるため、募集要項にもその年度の目標が記載されています。
事業の全体像を深く把握し、自治体が求める目的に沿った提案ができているかを確認します。
ときには、自治体の想定を超える付加価値を提案してくる事業者もいるかもしれません。目的への深い共感と理解がある事業者は、より良い成果を生み出す頼れるパートナーになりえます。
内容に具体性があるかチェック
提案書では、内容の具体性も確かめるべき重要な項目です。提案書そのものが、事業を運営する上での計画書として機能する水準に達しているかが、一つの目安です。
大前提として「何を」「いつまでに行うか」という実施内容とスケジュールが明確に記載されているかを確認します。
特にスケジュールの計画が甘いと、納期遅れといった問題が発生する危険性が高まります。具体的で実現可能な計画を提示できるかは、事業者の計画立案能力と実行力を測る上で重要な指標です。
STEP5:選定者に通知をする
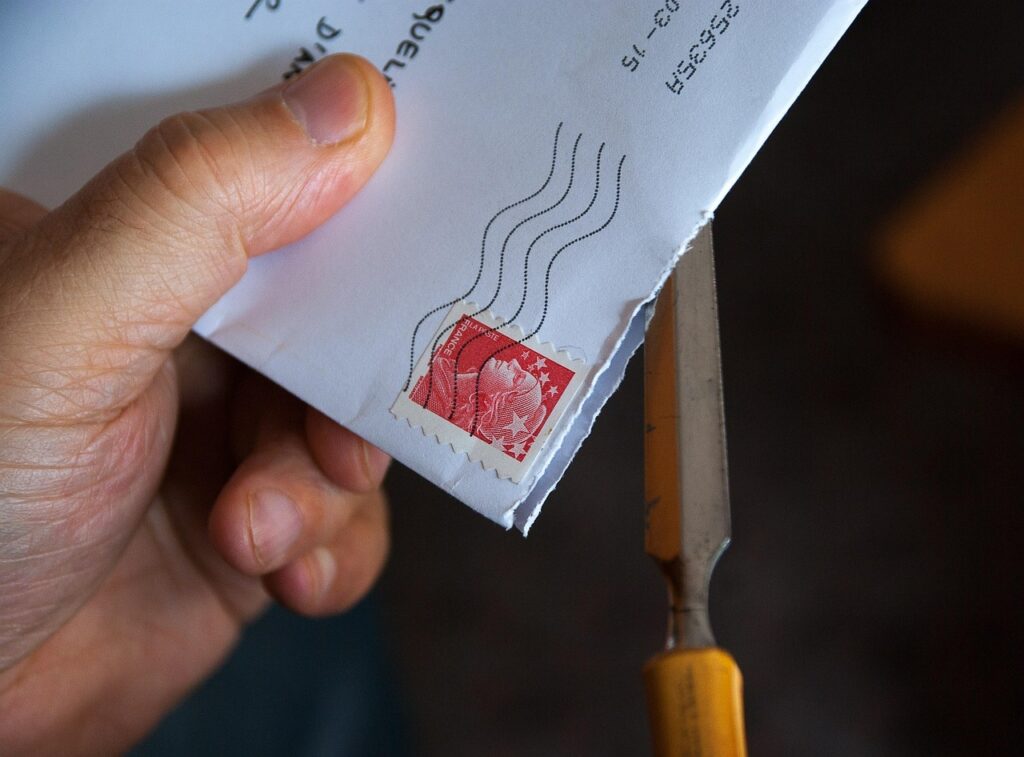
提案内容の審査が終わったら、選ばれた事業者に選定された旨を通知します。一般的には、書面を送付して知らせる方法がとられます。
一方で、残念ながら選ばれなかった事業者への配慮も大切です。選定されなかった理由を丁寧に通知するか、あるいは担当者からの説明要求に応じる機会を設けることが、事業者との良好な関係を築く上で望ましい対応といえます。
公平で誠実な対応を心がけることが、自治体の信頼性を高めることにもつながります。
STEP6:質疑応答でヒアリングをする
次に、選定した事業者から提案内容について、より詳しく話を聞くためのヒアリングを行います。
多くの場合、事業者がプレゼンテーションを行った後に、質疑応答の時間を設ける形で実施されます。
書面だけではわからなかった細かな点や、事業への熱意などを直接確認できる貴重な機会です。
ヒアリングを通じて、提案内容への理解をさらに深め、どの事業者が最も適しているかを慎重に判断します。
事業者との直接の対話は、最終決定を下すための重要な判断材料を提供してくれます。
STEP7:契約先を決定し契約締結をする
ヒアリングを経て、最終的に契約を結ぶ事業者を1社に決定します。その後、価格など契約内容の詳細について、事業者と交渉を進める段階です。
双方の合意が得られたら、正式に契約締結の手続きに入ります。提案書の特定から契約締結までにかかる期間は、およそ15日間が目安です。
この最終ステップを経て、計画された事業が本格的にスタートします。ここまでの手続きを丁寧に進めることが、事業の成功確率を高めるポイントです。
企画競争入札の種類
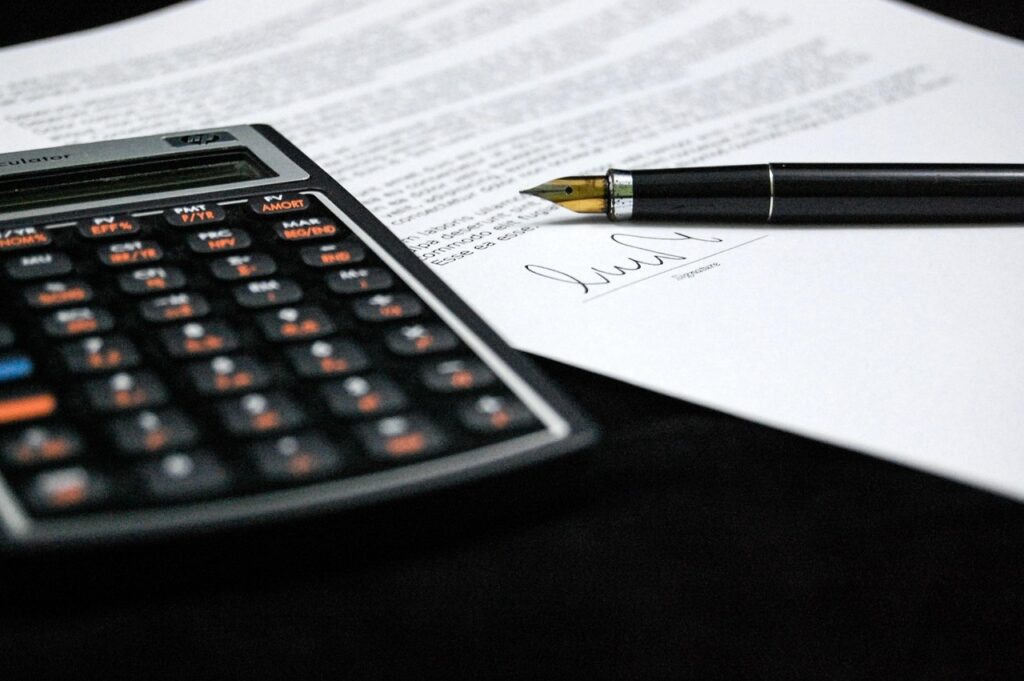
プロポーザル方式は、企画競争入札という大きな枠組みの中に含まれる方式です。
企画競争入札にはいくつかの種類があり、事業の特性に応じて使いわけられます。ここでは、主な3つの種類を紹介し、それぞれの特徴を解説します。
- 公募型プロポーザル方式
- 指名型プロポーザル方式
- 環境配慮型プロポーザル方式
公募型プロポーザル方式
公募型プロポーザル方式は、参加を希望する事業者を広く募集する方法です。自治体が定めた参加条件を満たしていれば、どのような事業者でも応募できます。
この方式の利点は、多くの事業者から多様な提案を集められるため競争性が高く、より優れたアイデアが生まれやすい点です。
価格競争に巻き込まれにくいのも、事業者にとっては魅力でしょう。
一方で、実績や経験が少ない企業は選ばれにくい傾向があり、提案書の作成やプレゼンテーションの準備に大きな労力がかかる点がデメリットとして挙げられます。
多くの事業者が参加する分、選定する自治体側の負担も大きくなる可能性があります。
指名型プロポーザル方式
指名型プロポーザル方式は、発注者である自治体などが、特定の企業を指名して参加を要請する方法です。
過去の実績や技術力を評価し、事業内容に適していると判断した事業者だけが参加します。
参加企業が限定されるため競争率が低く、指名された企業は受注につながる可能性が高いのがメリットです。発注者の求める条件に合っていると判断された企業が選ばれるため、質の高い提案が期待できます。
しかし、自治体から指名されなければ参加の機会すらないため、企業側は指名されるための戦略を考える必要があります。
自治体にとっては、新たな優良事業者を見つけるチャンスが減ることも考えられるのが指名型プロポーザル方式です。
環境配慮型プロポーザル方式
環境配慮型プロポーザル方式は、国や独立行政法人が大規模な建築物の建設や改修を行う際に採用する方法です。
事業者の選定において、環境への負荷をどれだけ減らせるかを重視します。受注できれば大きな利益が期待できる反面、温室効果ガスの排出削減をはじめ、高度な環境技術や専門知識が求められます。
企業にとっては、研究開発や専門人材の確保など、相応の投資と準備が必要になる点が特徴です。
環境への貢献と事業の収益性を両立させることが求められる、専門性の高い入札方式といえます。
自治体がプロポーザル方式を採用する2つのメリット

プロポーザル方式の導入は、自治体にとってどのような利点があるのでしょうか。ここでは、自治体がプロポーザル方式を採用することで得られる主なメリットを2つ紹介します。
- 業務のスピードアップが見込める
- 契約した後でも柔軟に交渉できる
これらのメリットを理解し、事業を成功に導きましょう。
業務のスピードアップが見込める
プロポーザル方式では、発注者と受注者が協力しながら事業を進めるため、円滑なコミュニケーションが可能になり、業務全体のスピードアップが期待できます。
何か問題が発生した場合でも、対話を通じて迅速に解決策を見つけられます。また、成果物の品質をともに管理しやすくなるため、納期遅れといった発注先との認識のずれを未然に防ぐことが可能です。
事業者との良好な関係性が、事業の推進力を高めるのです。
契約した後でも柔軟に交渉できる
プロポーザル方式は、提案内容と価格を総合的に評価して契約交渉に進むのが特徴です。契約内容については、発注者と受注者の協議によって変更することも認められています。
そのため、事業を進める中で状況が変化した場合でも、双方の要望を反映させながら、金額や納期などを柔軟に見直せます。
自治体側の都合や事情を反映させやすい点は、大きなメリットといえるでしょう。状況に応じた軌道修正が可能なため、より良い成果を目指せます。
自治体がプロポーザル方式を採用するデメリット

多くのメリットがある一方で、プロポーザル方式にはデメリットも存在します。企画内容だけでなく、提案する事業者自身も評価の対象となるため、事業規模の小さい会社や、地域での実績が少ない新規参入の事業者は評価されにくい傾向があります。
また、選定の過程では、透明性や公平性を証明する必要がある点も課題です。評価項目と点数を明確に定め、なぜその事業者を選んだのかを客観的に説明できなければなりません。
しかし、誰が見ても納得できるような詳細な評価基準を作成するのは、決して簡単な作業ではないでしょう。
これらの課題を認識し、対策を講じながら制度を運用する必要があります。
プロポーザル方式で最適な事業者を選出しよう!

本記事では、プロポーザル方式の概要から、自治体が利用する際の流れ、企画競争入札の種類、そしてメリット・デメリットを詳しく紹介しました。
プロポーザル方式は、価格競争に陥ることなく、事業の目的に最も合致した優れた事業者を選ぶための仕組みです。
手続きは複雑に感じるかもしれませんが、ひとつひとつのステップを確実に踏むことで、事業者との強固なパートナーシップを築き、事業を成功へと導けます。
「プロポーザルの仕組みが複雑で、どう進めたらいいかわからない」「制度を導入する際の調整に不安がある」といった課題も、この記事で解説したポイントを押さえれば、きっと解決の糸口が見つかるはずです。
ぜひ、本記事の内容を参考にして、あなたの自治体に最も適した事業者を選んでください。
指名競争入札に関してより専門的な情報を集めたい方は、株式会社リクロスのホワイトペーパーもご覧ください。
- URLをコピーしました!