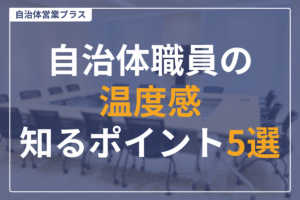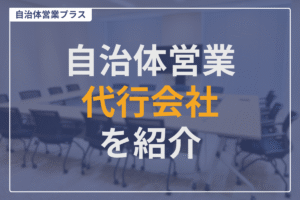随意契約とは?締結する手順や押さえるべき4つのポイントを解説

- URLをコピーしました!
随意契約の具体的な規定について詳しく理解できていない。
契約書を作成する際、適用条件を把握するのに時間がかかる。
随意契約の活用方法を知りたい。
このような悩みをお持ちではありませんか?本記事では、随意契約の概要や競争入札との違い、随意契約を締結する手順、押さえるべきポイントを詳しく解説します。
自治体営業をする上で、随意契約を正しく理解して戦略的に活かすことは非常に重要です。競争入札とは異なるこの制度を使いこなすことで、競合と差がつく営業が可能になります。
随意契約を理解し、自治体営業に活かしたい方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
随意契約の知識を深めることで、自治体営業の成功率を高められるでしょう。随意契約を自治体営業に活かすなら、株式会社リクロスのホワイトペーパーがおすすめです。
随意契約とは

随意契約とは、地方公共団体が特定の事業者と直接契約できる制度で、地方自治法施行令第167条の2に明記されています。競争入札が原則ではありますが、特定の要件を満たす場合に限り例外的に認められる契約手段です。
自治体の契約の大原則は競争性・透明性・公正性の確保ですが、随意契約はこれらの原則を損なわない範囲で、柔軟な契約手段として活用されます。
特に、入札にかけるほどの金額ではない場合や、時間的・技術的制約がある場合に用いられる傾向があります。
随意契約が認められる条件
以下のような条件で随意契約が認めれています。
- 少額契約(契約金額が自治体で定められた基準以下)
- 特定の技術や条件を満たす業者による履行が必要な場合
- 災害などの緊急対応が必要なケース
- 社会的配慮(障害者施設等からの調達)
- 政策的目的(地元企業支援や新商品導入など)
これらの条件が満たされていない場合、随意契約は違法または不適切な契約とされる可能性があります。そのため、自治体側も契約理由書を通じて「なぜ随意契約なのか?」を明示する必要があります。
随意契約の代表的な種類
随意契約には主に以下の類型があります。
少額随意契約: 物品購入80万円以下、工事130万円以下など、自治体ごとに定められた金額の範囲で実施されます。見積合わせにより複数社からの価格比較が行われる場合も多いです。
特命随意契約: 多くの企業が狙うのはこちらの特命随意契約になると思います。システム保守や特殊業務など、契約の性質上「この企業でなければ成り立たない」と判断される場合に限り認められます。自治体は必ず理由書で代替が利かない理由を説明する必要があります。
緊急随意契約: 災害時の緊急対応や修繕など、時間的余裕がない場合に用いられます。急ぎでお願いするほどなので、すでに関係がある事業者が優先される傾向があります。
政策的随意契約: 地元企業支援や新技術導入、新商品トライアルなど、政策目的が明確な契約形態で、自治体によって制度化されているケースもあります(例:東京都の新商品認定制度)。
随意契約における情報活用
随意契約に関する情報は多くの自治体で公開されています。具体的には、「随意契約結果の公表」ページや「契約締結状況報告書」、「入札・契約情報サービス(全国版)」などですね。
これらを分析することで、どの部署が・どの業務を・どのような理由で随意契約しているのかが見えてきます。競合企業の動きや金額の相場感も掴めるので、是非一度見てみてください。
随意契約と競争入札の違い

随意契約と競争入札の違いは、主に以下の2つの観点から解説できます。
- 一般競争契約との違い
- 指名競争契約との違い
それぞれの違いについて、以下で詳しく説明します。随意契約と競争入札の特徴を理解することで、適切な契約方法を選択できるでしょう。
一般競争契約との違い
一般競争契約では、全ての企業が参加するわけではなく、条件を満たした企業が参加可能です。一方、随意契約とは事業者の選び方が異なります。
一般競争契約は、複数の企業が競い合い落札しますが、随意契約は、特定の企業を自治体が指定する契約です。事業者の選定方法に大きな違いがあるといえるでしょう。
指名競争契約との違い
指名競争契約では、複数の事業者が選ばれ、その中で選定を行います。しかし、随意契約は特定の事業者を選定するため、その選定の手順が簡便です。
随意契約との違いは、2社以上を指名したうえで選定する作業の有無といえます。
指名競争契約は複数の企業からの選定作業や手続きが発生しますが、随意契約の方が、契約締結までの時間を短縮できるでしょう。事業者の選定方法と手続きの簡便さに違いがあります。
随意契約を締結する手順【3STEP】

随意契約を締結する手順は、主に以下の3つのステップで行われます。
- 見積書の作成・提出する
- 発注先を決定する
- 随意契約を締結する
それぞれのステップについて、以下で詳しく解説します。随意契約の締結手順を理解することで、スムーズに契約を進められるでしょう。
STEP1:見積書の作成・提出する
国または地方公共団体が随意契約を締結するに当たっては、受注者が提示する対価が適正であるかどうかチェックします。
そのため、随意契約の受注者候補である事業者は、相手方となる国または地方公共団体に対して見積書を提出する必要があります。
予定価格が高くなればなるほど、見積書を徴取すべき事業者の数が増える傾向にあります。また、2者以上の事業者から見積書を徴取した場合には、比較検討した上で受注者を決定するでしょう。
見積書の作成と提出は、随意契約締結の第一歩といえます。
STEP2:発注先を決定する
随意契約は入札(一般競争入札・指名競争入札)と異なり、安い価格で見積もりを出した事業者が自動的に選定されるわけではありません。発注者である国または地方公共団体が、総合的な観点から随意契約の受注者を選定します。
国または地方公共団体が締結する随意契約に関しては、そもそも見積もりの提示を依頼する段階で、信頼できる事業者をピックアップするのが一般的です。
各自治体が定めている随意契約のガイドラインでは、最も有利な(安い)価格で見積もりを提出した者を受注者に選定することが原則とされています。
公共工事等を受注するためには、競合他社の動向を分析しながら、適切な価格による見積もりを提示することが大切です。
総合的な観点から、発注先を決定するプロセスを理解しておくことが重要です。
STEP3:随意契約を締結する
随意契約の受注者に選定されたら、国または地方公共団体との間で随意契約を締結します。契約締結の手続きについては、通常の企業間における契約と基本的に同じです。
国または地方公共団体と、受注者それぞれの権限者が調印を行い、作成した契約書を双方が保管します。
随意契約の締結後、契約内容に従って公共工事等を実施するでしょう。契約締結のプロセスを理解することで、スムーズに業務を進められます。
随意契約を結ぶための4つのポイント

次に、随意契約を自治体営業に活かすには?という観点で解説していきます。
- 実績を積み上げる
- 発注機関との関係構築する
- 発注機関が抱える課題を把握する
- 緊急・地元優遇に備える
実績を積み上げる
少額随意契約は新規参入のチャンスです。まずは50~100万円前後の業務で丁寧な仕事を積み重ねることで次の契約に繋がります。
自治体にとっても「実績がある企業に継続的に依頼する方が安心」と信頼を獲得できます。
発注機関との関係構築する
随意契約はある程度「担当者が選びたいと思う企業」でなければ成り立ちません。わざわざ決め打ちするわけなので、当然信頼関係が重要となります。
こまめな情報提供や長期的に自治体と伴走する姿勢を示すなど、営業の基本を積み重ねましょう。
発注機関が抱える課題を把握する
発注機関が抱える課題やニーズを正確に把握し、それに合った提案ができる企業は、随意契約の獲得に有利になります。実際にアンケート調査を実施する企業もあるように、発注機関の課題感や動向を掴むことが大切です。
また、発注機関の予算計画や政策方針を事前に調査し、適切なタイミングでアプローチを行うことも効果的でしょう。発注機関のニーズに合致した提案を行うことで、随意契約の獲得につなげられます。
発注機関が抱える課題を的確に把握し、それを解決するソリューションを提示できる企業は、随意契約の受注で優位に立てるでしょう。発注機関の課題感を理解することが、随意契約獲得のカギとなります。
緊急・地元優遇に備える
災害時や緊急修繕など、スピード対応が求められる際には、普段からの関係がものを言います。私自身、市役所時代に台風による緊急修繕の対応をしたことを覚えています。
地元企業を優遇する調達方針を採用している自治体も多いので、自社が地元密着型であることを訴求するのが効果的なこともあるでしょう。
随意契約の3つのメリット

随意契約を結ぶメリットは、主に以下の3つが挙げられます。
- 高単価で受注できる
- 競争しなくても契約できる
- 受注者側に主導権がある
それぞれのメリットについて、以下で詳しく解説します。随意契約のメリットを理解することで、自治体営業の戦略を立てやすくなるでしょう。
高単価で受注できる
随契の場合、予定価格ギリギリで受注できます。予定価格を超過していても、予定価格の範囲内で契約額を協議できるので、金額を安くする必要がありません。
単独一社で行える随契は、一般的な入札とは大きく異なります。競争入札では、最低制限価格があるとした場合、予定価格の70.0%程度まで価格を落とさないと落札できないことが多いでしょう。
随意契約なら、高単価で受注できるメリットがあります。
競争しなくても契約できる
単独一社で契約となる随契は競争する必要がありません。入札となると競合がいくらで応札してくるかを想定して、金額を詰めなければ落札できません。
どれだけ落札したい案件であっても、競合がさらに価格を下回れば落札できないのが入札です。一方、競争する必要がない随契は100%受注者が落札できるのがメリットといえるでしょう。
受注者側に主導権がある
随契は発注者もその会社に頼まないと不利益があるからこそ行われます。
例えば、連続している道路工事で支障物が出て、施工中の業者でないと施工困難である場合や、施工箇所付近で緊急工事が必要になり、入札している時間がない場合などです。
このように、発注者としても随契で受けてもらえないと困ってしまう事情がある場合、受注者側に主導権があるといえるでしょう。
受注者側に有利な条件で契約を結べるメリットがあります。
随意契約を結ぶデメリット

随意契約を結ぶデメリットとしては、以下のような点が挙げられます。
- 当事者の一方が契約を守らないリスクがある、契約違反により損失が発生するリスクがある
- 契約内容の自由度が高いため、弱い立場の当事者が不利な条件を受け入れざるを得ないことがある
- 特定の法律や規制に縛られないため、紛争が生じた際の法的保護が不十分になる可能性がある
- 詳細が不十分なまま契約が成立することがあり、当事者間で誤解が生じる原因になる
- 明確な条件がない場合、当事者間の信頼関係が損なわれることがある
随意契約は、契約内容の自由度が高い反面、リスクも伴うことを理解しておく必要があります。
契約内容を明確にし、当事者間の信頼関係を築くことが、デメリットを回避するうえで重要でしょう。
随意契約の成功事例

随意契約の成功事例を以下に3つまとめました。
- 災害廃棄物処理業務
- 自治体HP保守業務の継続受注
- 地域振興プロジェクトの受託
①自治体HP保守業務の継続受注
某市の公式ウェブサイト構築を請け負った企業が、翌年度以降も保守業務を随意契約で継続受注といった例です。
理由書には「構築業者以外では仕様理解が難しく、トラブル発生時の対応も困難なため」と明記されていました。
初回受注時の導入戦略と信頼構築が鍵となった例ですね。
②地域振興プロジェクトの受託
地元商工会議所が、地域資源を活かした観光施策の企画・運営を随意契約で受託した例です。
選定理由は「地元住民・団体との調整力と信頼関係が必要不可欠であり、他団体では代替が困難」。
地域ネットワークや活動実績が評価される例であるとともに、説明ができれば随意契約にできる傾向が見られます。
③災害廃棄物処理業務
災害発生直後、既に過去に実績がある地元企業に廃棄物収集・処理を随意契約で依頼した例です。
「時間的余裕がなく、迅速な対応が可能な業者として妥当」と理由書に記載があり、緊急時にはすでに実績があるかが重要なことが分かるでしょう。
随意契約を自治体営業に活かすなら自治体営業プラスへ

本記事では、随意契約の概要から、随意契約と競争入札の違い・随意契約のメリット・デメリットを詳しく紹介しました。
随意契約を理解すれば、高単価で受注を獲得できたり、競争しなくても契約できるなど自治体営業に活かせます。
随意契約の知識をさらに深めたい方は、株式会社リクロスのホワイトペーパーがおすすめです。自治体営業の基礎知識から実践的なノウハウまで、幅広い情報を得られます。
自治体営業の戦略を見直したい方、新たな営業手法を取り入れたい方は、ぜひホワイトペーパーをダウンロードしてみてください。
自治体営業の専門家が、随意契約を活用した営業手法を詳しく解説しています。随意契約の知識を身につけ、自治体営業の成功を目指しましょう。
- URLをコピーしました!