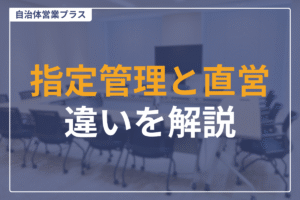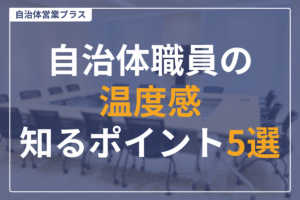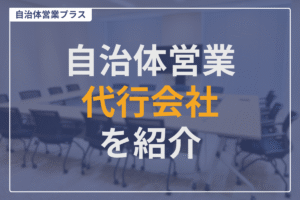【自治体営業】入札とプロポーザルの違いとは?営業ノウハウも解説
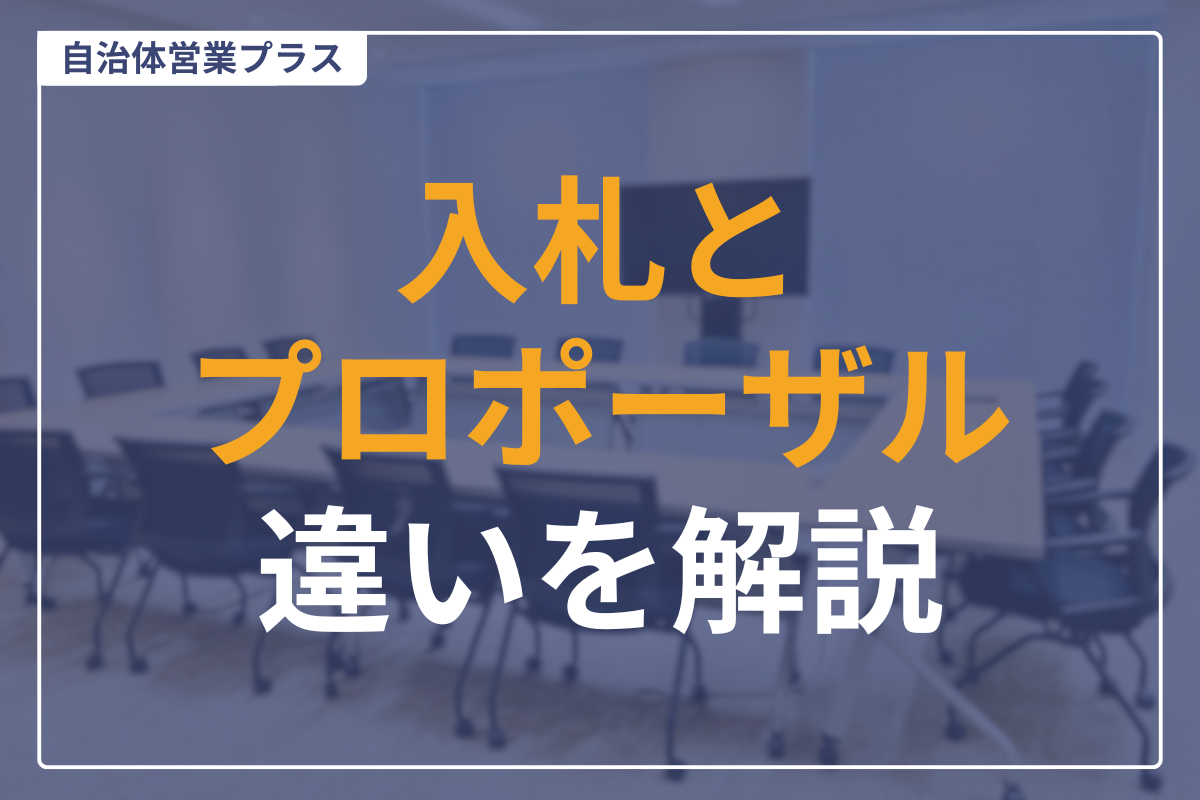
- URLをコピーしました!
はじめに
 木藤昭久
木藤昭久こんにちは!リクロスの木藤です。
今回は、自治体ビジネス初心者の方に向けて、入札とプロポーザルの違いについて解説します。
どちらも自治体案件を受注するための手段ですが、その内容や営業アプローチには違いがあります。
制度の違いから営業時の注意点まで、営業ノウハウとして応用できる形でご紹介します。
それでは見ていきましょう!
制度の違い
まず制度面の違いから見ていきましょう。
入札
入札は、主に工事や物品の購入など、仕様が明確な業務で使われる発注方式です。一定の参加資格を満たす事業者の中から「最も安い価格を提示した事業者」が原則として選ばれる、価格勝負の世界ですね。
公平性と透明性が求められる自治体業務において、入札は最もオーソドックスな発注方式です。基本的に自治体側が提示した仕様書をもとに、見積価格や過去の実績、企業規模などを加味しながら、厳格なルールに基づいて選定が行われます。
多くの自治体では「最低制限価格」を設定しており、過度なダンピング(極端な安値)も排除されています。
プロポーザル
一方、プロポーザル(正式には公募型プロポーザルや企画競争方式)は、提案内容をもとに評価される方式です。価格だけでなく、企画の独自性や実現性、体制や実績などが評価されます。例えば観光PRやシステム開発などでよく使われますね。
近年では「総合評価方式」を採用する自治体も多く、点数配分も例えば「提案内容7割・価格3割」といったバランスで内容の魅力が重視される傾向にあります。
営業アプローチの違い
次に、営業アプローチの違いについて書いていきます。
入札
入札については以下の点を押さえましょう。
- 価格がすべてなので、競合より安く出せるかが勝負
- 提案書作成の工数は少なめ
- 仕様が明確なので、提案の余地が少ない
- 入札情報は入札公告や調達情報公開システム、その他民間サービスなどから確認可能
- コスト削減と効率的な納品体制が重要
プロポーザル
プロポーザルについては以下の点を押さえてください。
- 自治体の課題やニーズを読み取った提案が求められる
- 提案書やプレゼンの準備に時間がかかる
- 提案内容次第で、多少価格が高くても選ばれる可能性がある
- プレゼンやヒアリング対応も含めた営業力が重要
- プレゼン本番だけでなく、事前の関係構築も非常に重要
自治体営業の際に意識すべきこと
入札とプロポーザルに関連して、自治体営業で意識すべきことを解説します。
①事業者登録を忘れない
入札もプロポーザルも自治体ごとに何かしらの参加要件があります(入札参加資格・事業者登録や書類提出など)が必要です。入札参加資格・事業者登録は年度単位の更新が必要な場合もあるため、常に有効期限を把握しておきましょう。
②自治体との関係構築
特にプロポーザルでは、日頃から自治体の職員と関係を築くことが重要です。
プロポーザルの採点表上では機械的に点数を付けているように見えても、選定委員も人間です。「いつも丁寧に情報提供してくれる会社」「現場に理解のある企業」に対して信頼が生まれ、選定委員に共有される可能性があります。
③提案書の分かりやすさ
プロポーザル選定委員の決め方の記事でも触れましたが、選定委員は必ずしも専門家ではありません。シンプルで明快に、自社の強みが伝わる内容を意識しましょう。
最後に
入札とプロポーザルの違いについて書いてきました。
- 価格勝負なら入札、提案勝負ならプロポーザル
- プロポーザルの提案は「読みやすく・伝わりやすく・差別化」できる内容に
- 日頃の関係構築と情報収集が重要
上記を念頭に置きつつ、是非他の記事もご参考にしていただければと思います。
今回もお読みいただきありがとうございました。
- URLをコピーしました!