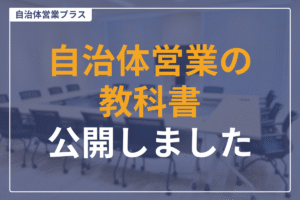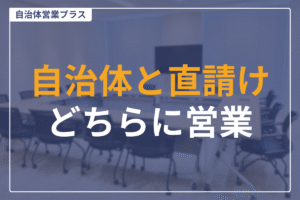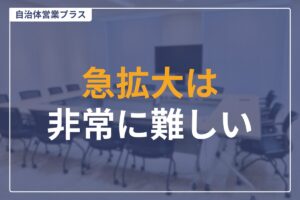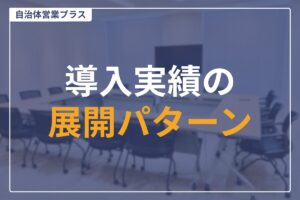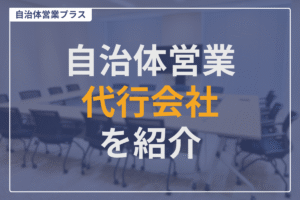自治体ビジネスでよくある参入障壁6パターン。対策にも触れます
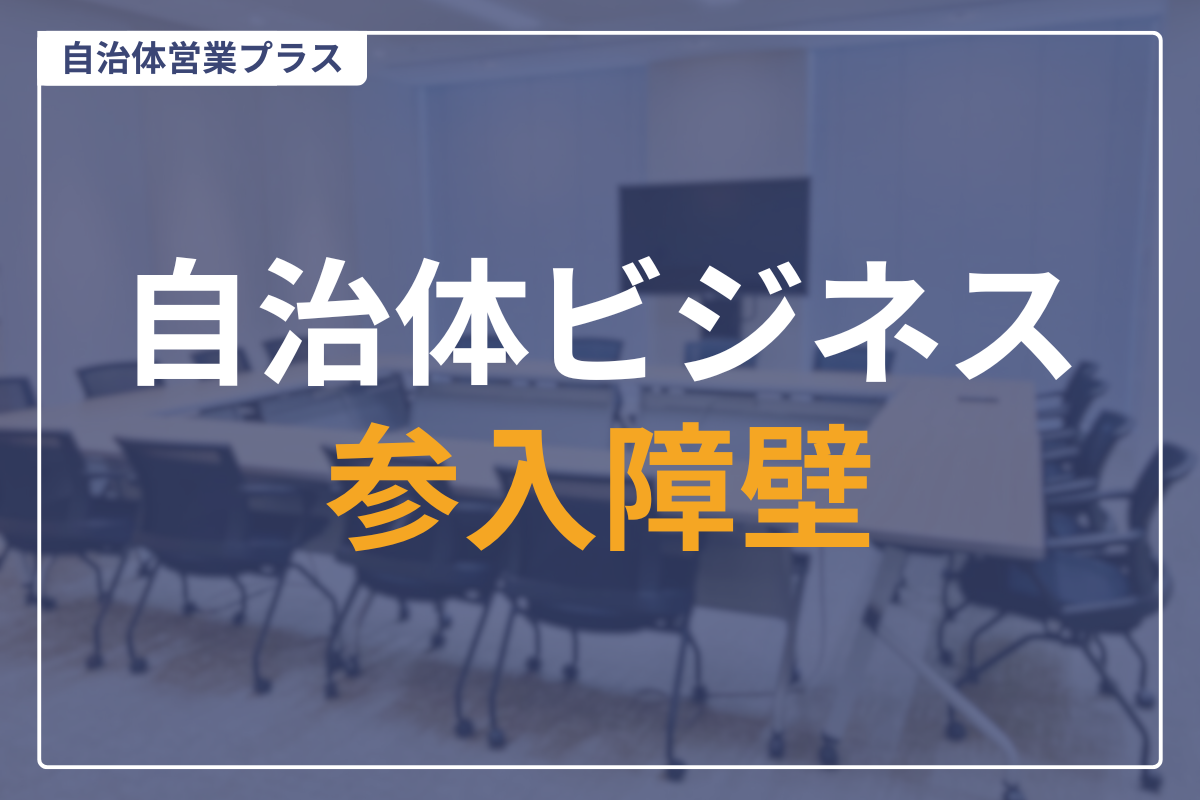
- URLをコピーしました!
はじめに
 木藤昭久
木藤昭久こんにちは!リクロスの木藤です。
今回は、自治体ビジネスでよくある参入障壁を6パターン解説します。
自治体の調達において、「仕様書が公開されたときにはすでに勝負がついている」といった話を聞いたことのある企業様もいらっしゃるのではないでしょうか。
実際、仕様書は多くの場合、すでに自治体と関係性のある民間企業が関わって作成されることが多く、その企業に有利となるような参入障壁(他社の参入を阻む条件)が盛り込まれていることもあります。もちろん自治体のルールを守った上でです。
本記事では代表的なパターンや対策をご紹介します。
それでは見ていきましょう!
参入障壁は自治体や企業が意図をもって設ける
行政の役割上、自治体は建前上「誰にでも開かれた契約先」であることを求められます。
しかし、例えば誰にでも開いた結果、数十社の参加になってしまうと、1社を決めるのに事務負担のみが膨大になってしまいます。
また、担当レベルでは「この会社に発注したいな」と思うのは自然な感情です。そこで条件を絞り、参加者数を減らす動きを取ることは珍しくありません。
また、営業する企業が自社に有利な条件にするのも当然でしょう。自治体ビジネスは入札やプロポーザルからいきなり参加・受注できてしまうことがありますが、最初からアプローチや打ち合わせ、現場視察、仕様書作成、見積書作成、予算要求フォローなどを重ねた企業としては「絶対うちで自社で受注したい」と考えているはずです。
要するに、一緒に検討を進めた自治体と企業は利害が一致するわけです。
参入障壁の6パターン
参加資格:形式要件で門前払いされるケース
自治体では、入札参加の条件として以下のような資格を求めることがあります。
- 過去数年以内の同様業務の実績
- 本店・支店の所在地が市内や県内にあること
- 建設業許可、ISO認証、特定技術資格などの保有
これらは一見公平に見えますが、特定企業だけが満たしている条件を盛り込むことで、新規参入企業の排除につながります。
例えば「過去3年間に同程度の規模の自治体で類似業務を◯件以上実施」と記載されていれば、新規企業は実質的に参加不可です。
公示後にできる対策はないので、営業段階から実績づくりや拠点設置するなど事前の活動が必要となります。
一者随意契約:そもそも競争にならない仕組み
随意契約とは、競争を経ずに特定の1社と直接契約を結ぶ方式で、特に以下のようなケースで多く見られます。
- 過去に同様の業務を委託しており、継続性が重視される
- 対象製品が特殊で代替がきかない
この場合、他社は情報すら得られないこともあるのが実情です。
業務内容:技術やノウハウに依存した内容設計
仕様書における業務内容の記述が、特定の技術や製品、ノウハウに強く依存していることがあります。例えば、
- 特定の会社のシステムとのAPI連携が可能なこと
- 技術的には開発可能だが時間がかかり間に合わない
こういった内容であれば、参加できる企業が絞られることが分かるでしょう。
予算:他社が見積もると赤字になる価格設定
表面上は誰でも参加可能に見える案件でも、予算額(提案上限額)が低いことで参入を阻む例があります。
- 必要な人件費や材料費を考えると明らかに採算が合わない
- 委託費よりも間接コストの方が高くなる
予算額を超えて落札することはできないに等しいので、予算内で実施できない場合は対抗のしようがありません。
評価基準:特定企業に有利な配点設計
自治体の入札やプロポーザルにおける評価項目と配点の設計は、業務内容を鑑みて設計され、以下のような特徴がある場合は特定企業に有利となっている可能性があります。
他自治体の案件と比べ露骨に実績や価格の配点が高い場合、自治体や企業の意図が含まれている可能性があるでしょう。
準備期間:公告から締切までが極端に短い
公告から提出締切までの期間が非常に短い案件も注意が必要です。例えば、
- 公示から5営業日で企画書提出
- 連休を挟むスケジュールで準備時間が少ない
このような案件では、あらかじめ情報を得ていた企業でないとなかなか対応できません。
最後に
お気づきでしょうが、これらの参入障壁は公示後に対抗できないことがほとんどであり、だからこそ参入障壁として成り立ちます。
仕様書作成に関わらないことには基本どうしようもないですし、自治体が「これから仕様書を作成します!」と公表するわけではないので、事前に接点を持ち信頼を重ねておく必要があります。
自治体ビジネスは入札やプロポーザルからいきなり参加できることがありますが、それだけでどんどん受注を重ねられるほど甘くないのが私の率直な印象です。
リクロスではアポ獲得や商談実施などの営業支援を行っていますので、興味があれば是非資料請求してください。
以下のホワイトペーパーも参考になれば幸いです。
- URLをコピーしました!