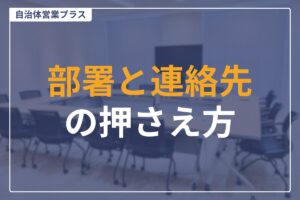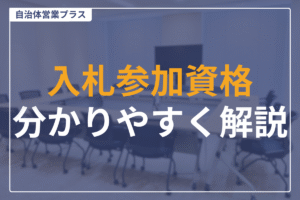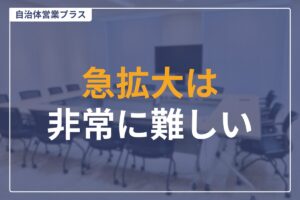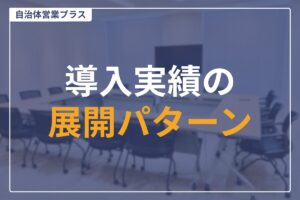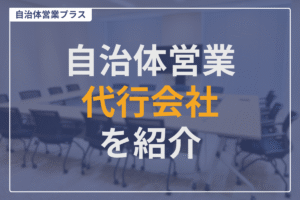【考察】自治体職員の行動背景を考える補助線【自治体営業】
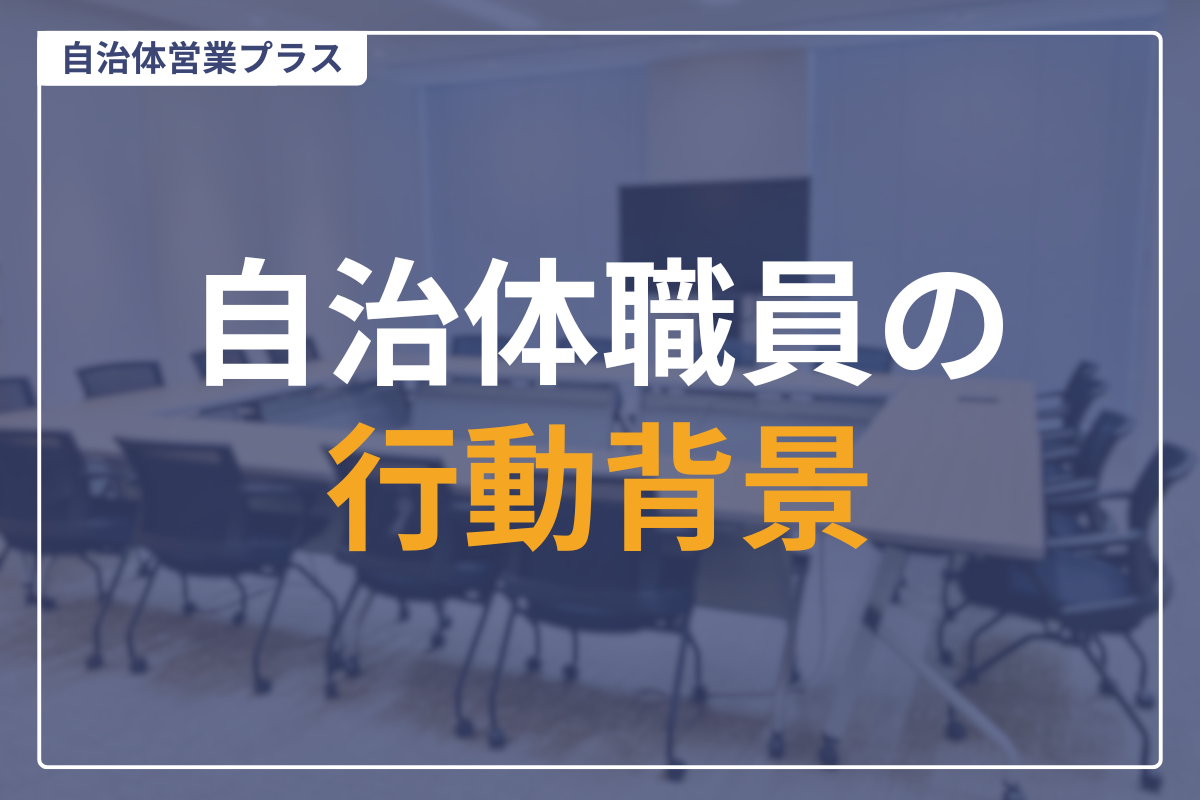
- URLをコピーしました!
はじめに
 木藤昭久
木藤昭久こんにちは!リクロスの木藤です。
今回は、自治体営業に取り組む民間企業の営業担当者向けに、自治体職員の行動背景を理解するための3つの視点をご紹介します。
私自身、市役所・中央省庁への出向・リクルートでの法人営業を経て、現在は自治体営業の支援事業を行っています。行政側・営業側の両方を経験してきたからこそ見える視点として、「ルール」「空気」「裁量」という3つの補助線を意識することで、自治体営業がぐっと進めやすくなるという実感があります。
それぞれの補助線について、私の経験も交えて解説していきます。
それでは見ていきましょう!
自治体職員の行動背景を考える補助線
①ルールがある
まず最初の補助線は「ルール」です。自治体営業に取り組まれる方はご存知だと思いますが、自治体職員の行動は、条例や要綱、予算、契約規則など明文化されたルールによって大きく制限されています。
営業の場面でも、「まずは次年度の予算に計上する必要がある」「この契約形態だとプロポーザルが必要になる」など、いかに職員がルールに従って行動しているかが分かります。
私が市役所に勤務していた頃も、どれだけ良い提案でも予算が付いていなければ検討すらできないというケースがありました。
言うまでもありませんが、「ルール」があれば自治体職員は必ず守ります。ルールを守ることが自身や組織を守ることに繋がるので当然ですよね。
「役所は多くのルールがある」ということを分かっている方は多く、いろいろな知識を詰め込むのも重要ですが、以降の「空気」「裁量」という視点があると一層解像度が高まります。
②空気がある
二つ目の補助線は「空気」です。ここでいう空気とは、世間からの目や組織内の風潮など、明文化されていない雰囲気のことです。
自治体職員は「税金を使っている立場」であることから、常に住民やメディアの視線を気にしています。何かあったときに「税金の無駄遣いだ」「公平ではない」「不正しているだろ」などと言われないよう、とにかくリスクを避けたがる傾向があります。
パッと思いつくだけでも、「空気」が理由で以下の行動などが見られます。
- アポを断れず資料送付を依頼する
- 電話でいい加減な対応ができない
- 手土産などを受け取れない
- 「導入します」などと断言できない
- 営業を断れず予算がないことにする
- 予算要求していないことを言えず、財政課の査定で切られたことにする
世間にバッシングされないためには、説明責任を果たせる材料を提供すると良いでしょう。具体的には、
- 人口規模や位置が近い自治体での導入実績があることを伝える
- 第三者評価(例:〇〇省の採択事業等)があることを示す
- 誤解を生まない表現・プロセスを選ぶ
などですね。
正当性・客観性のある提案をもって「空気」に配慮したアプローチを重ねましょう。
③裁量がある
三つ目の補助線は「裁量」です。ルールや空気に縛られているように見える自治体職員ですが、それらをクリアした上で「裁量」が発揮できる部分があります。
自治体営業に関連する場面では、例えば以下のことができます。
- 他社に見積書を依頼しない(「3社の見積書を集めればOK」という運用であれば、わざわざそれ以上の見積を集めない)
- 他社に仕様書をチェックしてもらわない(「〇社にチェックしてもらう」というルールがない)
- 予算要求している旨を伝えない(伝えるというルールはない)
- 予算が確保できたことを伝えない(伝えるというルールはない)
- 随意契約にする(ルールを守りつつ合理的に説明できるのであれば随意契約にできる)
- 随意契約にしないものの、参入障壁のある仕様書にする(仕様書の全てがルールに縛られているわけではない)
- 公示したことを伝えない(ルール上、公示を伝える義務はない)
- HPでの公示をすぐに終える(ルールとして日数に定めがなければ可能)
- 公示からプロポーザルまでの期間を短くする(ルールを満たす範囲で最短にすることは珍しくない)
これらは意中の一社に決定させるために行われることが多いです。
すでに自治体ビジネスに取り組まれている企業様であれば、身に覚えがあるものがいくつかあるでしょう。「ルールを守り・説明責任を果たした上で、特定の事業者が選ばれやすいように見えるプロポーザル」などは決して珍しくありません。
最後に
自治体営業において、職員の行動が読みにくい・動いてくれないと感じたときは、今回ご紹介した3つの補助線「ルール」「空気」「裁量」を意識してみてください。
ルールを守り、空気に配慮して説明責任を果たし、裁量をうまく使ってもらえるような営業活動が理想です。
営業担当者として、職員の立場や判断の背景を正しく理解することで信頼を得て、成果を上げることができると思います。
本記事が自治体営業におけるヒントになれば幸いです。
- URLをコピーしました!