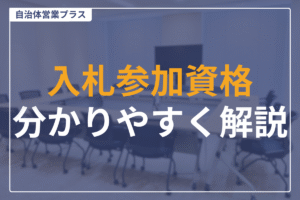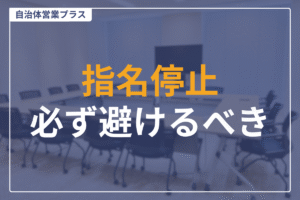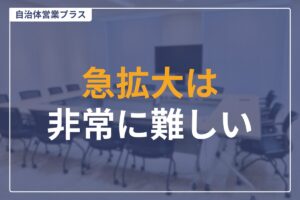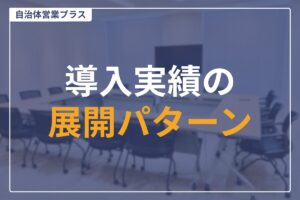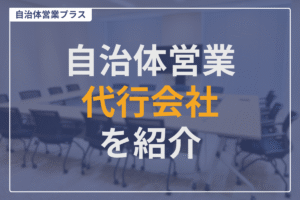【自治体営業】中央省庁の予算編成スケジュールについて
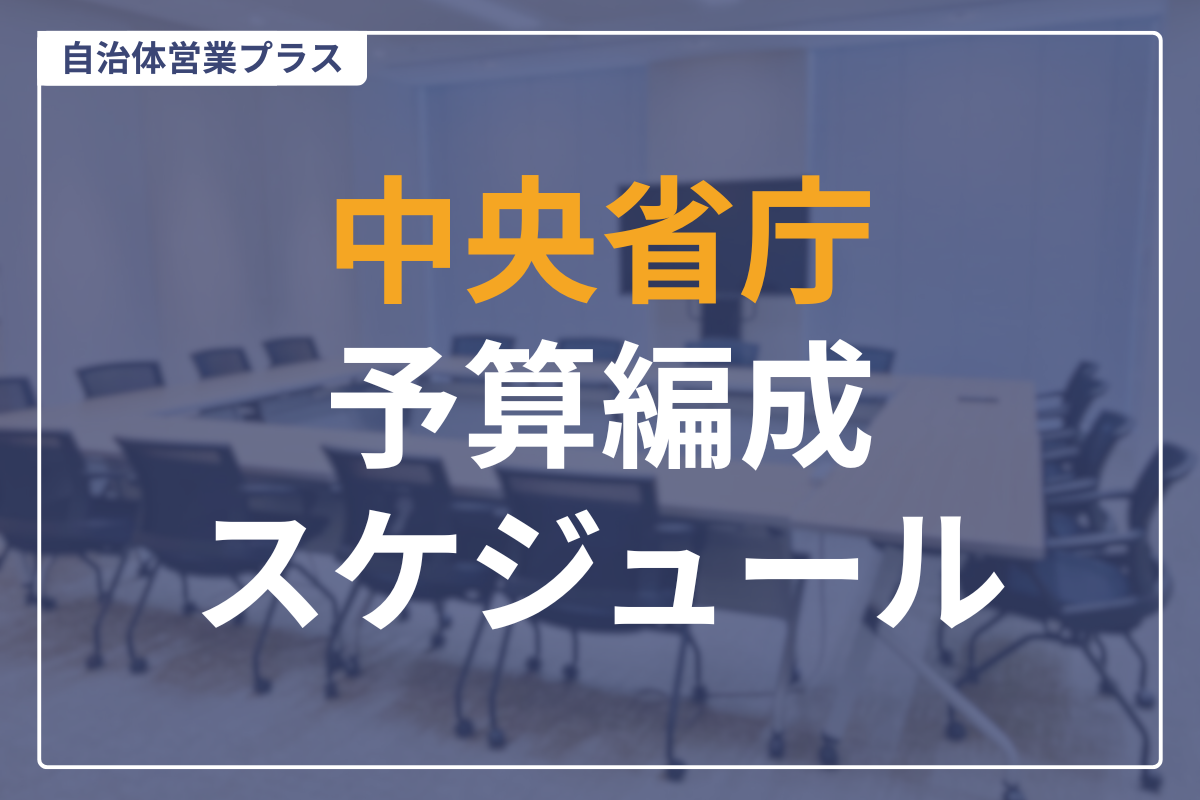
- URLをコピーしました!
はじめに
 木藤昭久
木藤昭久こんにちは!リクロスの木藤です。
今回は、中央省庁の予算編成スケジュールについて書いていきます。
普段の自治体営業では都道府県や市区町村を対象にした活動が中心になりますが、その背景には中央省庁の予算があります。
つまり、国の予算の動きを把握しておけば「なぜこのタイミングで自治体が動き出したのか」「来年度に向けてどんな分野がチャンスか」など見えてくるようになります。
それでは早速見ていきましょう!
中央省庁の予算編成スケジュール
中央省庁の予算編成スケジュールについて、概要を以下の表にまとめました。
| 時期 | 主な動き | 営業で押さえたいポイント |
|---|---|---|
| 4~6月 | 各省庁内で翌年度施策の政策検討開始 | 審議会資料や検討テーマをウォッチしておく |
| 6月下旬 | 骨太の方針(基本方針)が閣議決定 | 重点キーワードを抽出し、業界トレンドを先読みする |
| 7月下旬 | 概算要求基準を財務省が提示 | 予算全体の方向性を把握する |
| 8月末 | 各省庁が概算要求を提出・公開 | 数字付きで狙い目の分野を特定しておく |
| 9~11月 | 予算査定(財務省と他省庁間) | 関連団体・議員連携など間接的な働きかけの余地あり |
| 12月下旬 | 政府予算案が閣議決定 | 具体的な補助金メニュー確定。企画を具体化する時期 |
| 1–3月 | 通常国会で予算審議 | 公募の事前告知にアンテナを張る |
| 4月 | 新年度開始・予算執行スタート | 補助金公募が本格化。即提案できる体制を取っておく |
スケジュール詳細
次に詳細を見ていきましょう。
4月〜6月:各省庁で政策の検討が始まる
新年度が始まったばかりですが、すでに次年度の準備が始まっています。
各省庁で課題やニーズを整理し、外部有識者の会議(審議会や分科会)を通じて翌年度に向けた施策を検討します。
民間企業や自治体からの提案が施策立案のタネになる可能性があり、この時期に各省庁の動向や審議会資料をウォッチしておくと概算要求の方向性が見えてくるでしょう。
6月下旬:政府の「骨太の方針」が閣議決定
内閣府が主導し、政府全体の経済政策の方向性をまとめた骨太の方針が決定されます。骨太の方針には来年度政府が重点的に取り組むテーマが盛り込まれます。例えば、
- 地域脱炭素(GX)
- 子育て支援強化
- 自治体DX・マイナンバー促進
- 防災・国土強靭化
など営業のヒントとなるキーワードが満載です。
7月下旬:概算要求基準が決定される
財務省が概算要求基準を閣議了解します。概算要求基準は、各省庁がどれだけの金額を要求してよいか、また、例外的に上乗せできる重点枠(特別枠)などのルールを定めたものです。
この段階で「来年度予算は厳しい」「重点枠が広がりそう」など、予算全体の傾向が読めるようになります。
8月末:各省庁が概算要求を提出・公表
ここが前半戦のクライマックスとなります。
各省庁は自省の概算要求をまとめ、財務省に提出します。同時に、その概要がメディアや省庁HP上で公表され、翌年度の国の動きが見えてくるタイミングです。
例えば、経産省が「スタートアップ支援に〇億円要求」、総務省が「自治体の標準化に〇〇億円」など、数字とともに明示されます。
このタイミングで「来年度、こんな予算枠がつきそうですね」という形で自治体との会話のきっかけになるでしょう。
9月〜11月:財務省と省庁の調整(予算査定)
提出された概算要求をもとに、財務省主計局が査定を行います。ここからは、各省庁の担当者と財務省主計官との水面下の調整がメインになりますね。
一応この期間も、自治体や民間が間接的に影響を与えられる時期でもあります。例えば、関連団体からの陳情や業界団体の要望、議員連携による調整などが反映されることもあります。
12月下旬:政府予算案が閣議決定
年末には政府予算案として、各省庁の要求が調整された内容が閣議決定され、このタイミングで具体的な補助金や交付金の内容・規模が確定します。
以下に例をまとめます。
| 施策分野 | 所管省庁 | 予算名の例 |
|---|---|---|
| 自治体DX | 総務省 | 自治体情報システム標準化支援事業費 |
| 地方創生 | 内閣府 | 地方創生推進交付金 |
| 公共施設改修 | 国交省 | 社会資本整備総合交付金 |
| 福祉・保育 | 厚労省 | 保育所整備費補助金 |
1月〜3月:通常国会での予算審議
年明けからは、通常国会で予算案が審議されます。この期間はテレビなどで総理大臣や大臣が答弁する場面を見ることも多くなりますね。
基本的にこの時期は予算の成立を待つ段階ですが、補助金公募の事前告知などが始まる省庁もあります。
4月以降:新年度開始、予算執行スタート
予算が成立し、いよいよ各事業がスタートします。補助金の正式な公募が始まるのもこの時期です。
自治体営業での活用ポイント
ここまでのスケジュールを自治体営業の戦略に落とし込むと、以下のようになります。
5〜7月
自社事業が国の重点施策に入りそうかをチェックしましょう。関連省庁に要望・提案を持ち込むチャンスの時期でもあります。
8〜9月
概算要求をチェックして、関連分野の動きを把握しましょう。自治体に対して予算化されそうな施策の情報提供もできると接点量を増やすことができます。
12〜1月
政府予算案から補助金の内容をチェックしましょう。予算に沿った企画を作り込み、営業準備を本格化できると良いです。
2〜3月
自治体の予算審議と連動して提案をブラッシュアップしましょう。企業内での人事異動もあるかもしれませんが、4月からすぐ動ける体制づくりができるのが理想です。
最後に
中央省庁の予算編成スケジュールについて書いてきました。
表に出てくる情報(補助金の公募など)はごく一部に過ぎず、その背景にあるプロセスまで理解しておくと他社よりも一歩先を行くことができるかと思います。
本記事を参考に、営業戦略のカレンダーに中央省庁の動きも是非組み込んでみてください。
- URLをコピーしました!