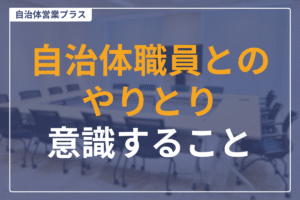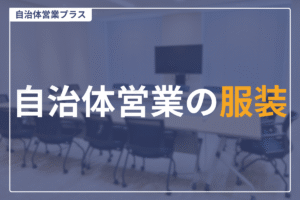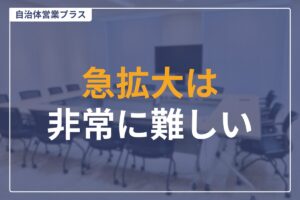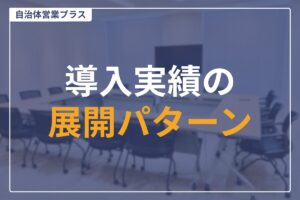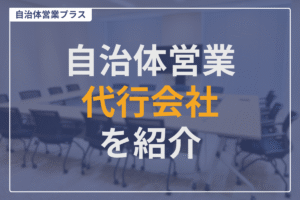自治体営業と民間営業の違いとは?似ている点やメリット、難しい理由を解説
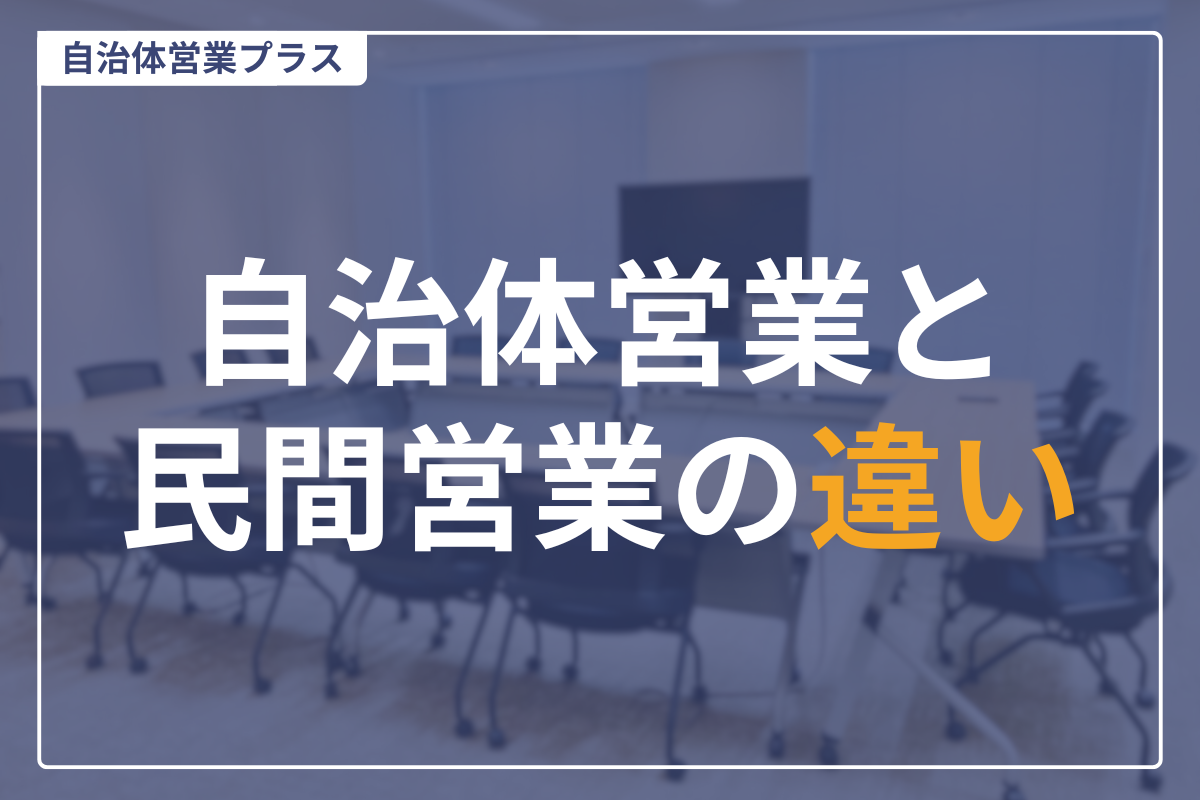
- URLをコピーしました!
 木藤昭久
木藤昭久こんにちは!リクロスの木藤です。
今回は「自治体営業は難しいか?」について私なりの見解を書いていきます。
世間的には「難しい」「取っつきにくい」「面倒が多そう」という印象があると思いますが、本記事をご覧いただいて自治体営業を考えるきっかけとなれば幸いです。
なお、以下より全110ページのホワイトペーパー『自治体営業の教科書』を無料ダウンロードできますので、興味がある方は是非ダウンロードしてください。
それでは早速見ていきましょう!
自治体営業とは?


自治体営業とは、市役所や区役所、町村役場などの自治体に対して行う営業活動のことです。
企業間で行われる営業活動とは異なり、自治体営業では市民の生活が重視されることが特徴の1つです。そのため、自治体に対しては社会的意義や成果指標を明確にする必要があります。
また、単なる利益追求ではなく、地域社会への貢献や課題解決につながる提案が求められるのが自治体営業の特徴でもあります。
さらに詳しく知りたい方はこちらの記事も合わせてご覧ください。
関連記事:自治体営業とは?難しい理由や流れ・5つの成功のコツまで徹底解説【営業のプロ監修】
民間営業とは?


民間営業とは、企業が他の企業や個人に対して行う営業活動のことです。
多くの企業が存在しているため、基本的に競争率が激しい傾向にありますが、価格やサービス内容の柔軟性が高いことが特徴です。また、民間営業では担当者同士の信頼関係などが重視されることが多いため、価格やサービス以外の観点から取引が進むケースもあります。
そのため、民間営業では商品やサービスの価値を伝えつつ、人間関係を築くことが営業成功のカギを握ると言えます。
自治体営業と民間営業との違い
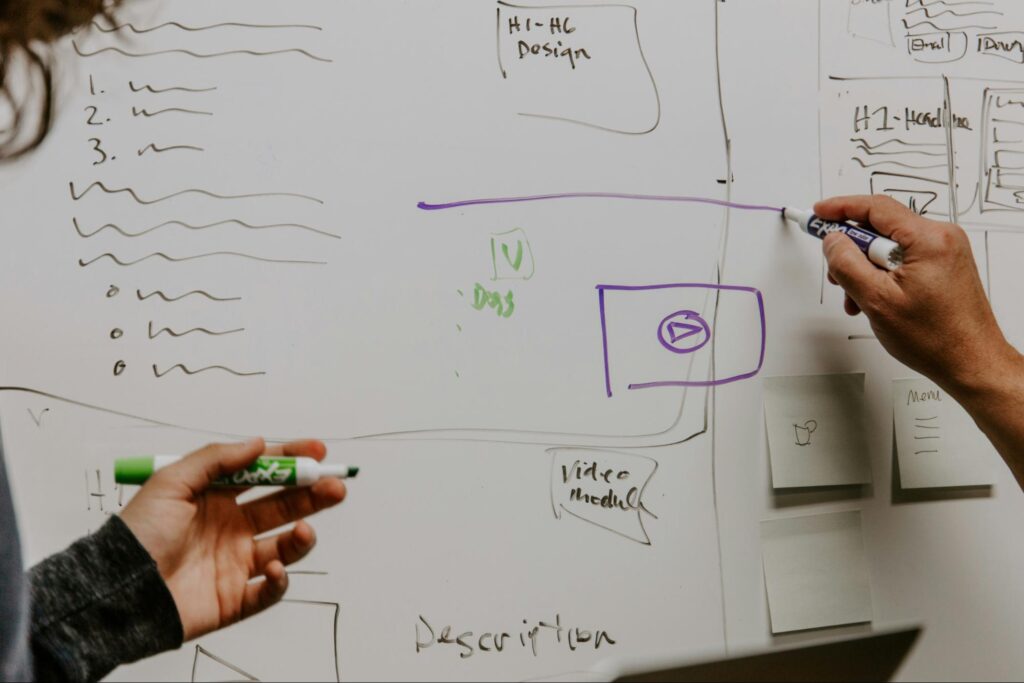
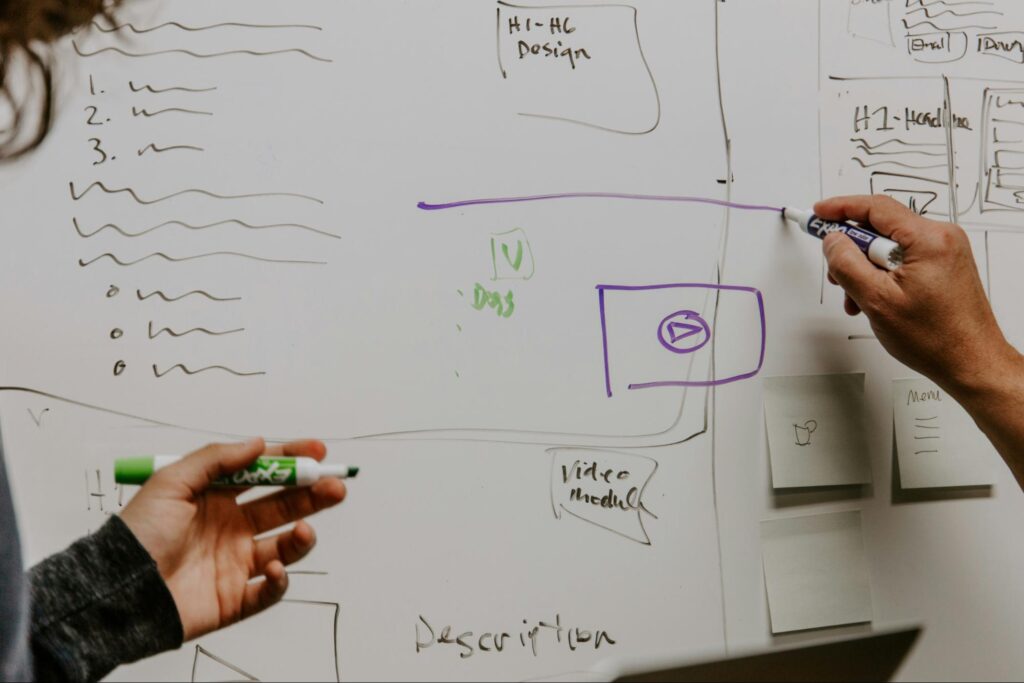
自治体営業と民間営業との違いは、主に以下の通りです。
| 項目 | 自治体営業 | 民間営業 |
| 意思決定スピード | 入札や稟議などで時間がかかる | 担当者の判断でスピーディに決まることが多い |
| 契約プロセス | 公平性や入札基準を確認して契約する | 価格や内容を柔軟に交渉し契約する |
| 評価基準 | 法令遵守や価格、実績など | コストや品質、人間関係など |
| 営業体制 | 書類作成や入札対応など | 関係構築やプレゼンなど |
自治体営業と民間営業には、上記のような違いがあります。これから自治体営業を行う企業は、これらの特徴を理解した上で実施することが大切でしょう。
自治体営業が法人営業と似ている5つの点


自治体営業が民間営業と似ている点は、主に以下の5つです。
- 意思決定が遅い
- 独特のルールや制度の存在している
- 関係構築に時間がかかる
- 予算スケジュールへの対応が必要になる
- 透明性と説明責任が求められる
それぞれの点について、以下で詳しく解説します。
自治体営業と民間営業の共通点を理解することで、営業戦略を立てやすくなるでしょう。
意思決定が遅い
意思決定が遅いのは、民間大手にもありがちな事情でしょう。
大企業やグローバル企業でも意思決定には多くのステークホルダーが関わるため、商談成立までに時間を要します。
自治体の場合も同様に、担当部署や上司、場合によっては議会や住民の理解と合意が必要となるだけで、「多層的な承認プロセスがある法人への営業」と考えれば、全く特別なことではないでしょう。
独特のルールや制度の存在している
自治体営業における独特のルールや制度の存在は、法人営業における業界特有の規格・安全基準などと類似しています。
自治体には入札制度や補助金交付基準などに基づく手続きを要することがあり、それらが「難しい」と思われがちです。
しかし、建築業界であれば建築基準法や各種認証、医療業界であれば薬機法対応といった業界特有のルールへの適応が不可欠です。
自治体営業も一つの「業界規則」と認識すれば、特異なハードルではなく「慣れれば対処できるルール」でしかないでしょう。
関係構築に時間がかかる
自治体営業で関係構築に時間がかかるのは、法人営業における既存顧客の深耕営業と同じです。
自治体職員は異動が多く、人間関係をゼロから築く必要が出てきますが、多くの法人営業でも担当者が変わったり、組織再編により取引条件を再交渉したりするケースは全く珍しくありません。
既存顧客との関係維持という観点でも、担当者や組織変更が起これば最初からコミュニケーションを設計する必要があるため、「自治体だから難しい」わけでなく「法人営業ならあり得ること」と捉えることができるでしょう。
予算スケジュールへの対応が必要になる
自治体営業における予算スケジュールへの対応は、法人営業における期末商戦や大企業の年度計画対応に似ています。
自治体は年度ごとに予算が決定・消化されますが、大企業も同様に年度末や四半期末に調達判断が集中するケースがありますよね。
自治体営業で「この時期は動きが悪い」「ある時期に一気に話が進む」といった傾向は、民間の法人営業でも「期末商戦」や「決算前の駆け込み発注」といった形で起こります。
つまり、予算スケジュールへの対処は特別なことではなく、法人営業における季節性や予算を意識した戦略立案と同様です。
むしろ、全国の自治体が同じようなスケジュールで運営されているので、自治体営業の方が簡単だと言わざるを得ないでしょう。
透明性と説明責任が求められる
自治体営業における透明性と説明責任は、法人営業におけるコンプライアンス重視企業への提案と似た課題でしょう。
自治体は公的機関として公正性と透明性が求められ、提案を受け入れる際には説明責任が伴います。
これも、株主対応や社会的責任を強く問われる上場企業や新興規制業界における営業と類似しており、相手の求める透明性基準やプロセスを理解して対応するだけの話ですね。
自治体営業を実施する3つのメリット


自治体営業を実施するメリットは、主に以下の3つです。
- 法的違反のリスクがほとんどない
- 自社の信用やブランド力が向上する
- 販路を拡大できる
それぞれのメリットについて、以下で詳しく解説します。また、自治体営業のメリットを理解することで、営業活動への意欲を高められるでしょう。
法的違反のリスクがほとんどない
自治体営業を実施するメリットは、法的違反のリスクがほとんどないことです。自治体相手に行うビジネスでは、未払いや手続きや法令上のトラブルが起きにくいため、安心して取引や営業を行うことができます。また、民間企業との取引と比べて、リスク管理の負担が少ないのが自治体営業のメリットと言えるでしょう。
自社の信用やブランド力が向上する
自社の信用やブランド力が向上することも、自治体営業を実施するメリットの1つです。
自治体との取引を進める場合、厳しい規則や条件をクリアしなければいけない場合があります。そのため、自治体と取引している企業は社内整備が整い、他社からの信頼も高くなりやすいでしょう。
自治体との取引実績は、自社の信用力向上につながるため、検討してみることがおすすめです。
販路を拡大できる
自治体営業を実施することで、販路を拡大できるようになります。
特に、これまで民間企業との取引経験しかない企業であれば、全く新しい分野へ参入することになるでしょう。また、自治体は全国にあり安定していることが多いため、自社にとって重要な販路になる可能性があります。
そのため、自治体営業を実施することで、新たなビジネスチャンスを獲得できる機会が増えます。
自治体営業は難しいと言われている4つの理由


自治体営業が難しいと言われている理由は、主に以下の4つです。
- 民間営業とは営業プロセスが異なるため
- 人脈やコネを使った営業が通用しにくいため
- 加点方式ではなく減点方式で評価されるため
- 入札・プロポーザル制度の仕組みが複雑なため
それぞれの理由について、以下で詳しく解説します。
自治体営業の難しさを理解することで、適切な対策を立てられるでしょう。
関連記事:自治体営業とは?難しい理由や流れ・5つの成功のコツまで徹底解説【営業のプロ監修】
民間営業とは営業プロセスが異なるため
自治体営業が難しいと言われている理由は、民間営業とは営業プロセスが異なるためです。
民間営業であれば、担当者と交渉して柔軟に契約を進められますが、自治体営業の場合は公平性や入札基準を確認して契約するため、知識や経験がない場合は成約が難しいでしょう。
自治体営業を成功させるためには、自治体特有の営業プロセスを理解することが大切なポイントです。また、民間営業とは異なるアプローチが求められるため、営業戦略の見直しが欠かせません。
人脈やコネを使った営業が通用しにくいため
人脈やコネを使った営業が通用しにくいことも、自治体営業が難しいと言われる理由の1つです。
自治体は数年で人事異動が起きる場合があるため、担当者との信頼関係を深めることが難しいです。そのため、自治体営業では営業力や提案力、商品・サービス力が、民間営業よりも重要視される傾向にあります。
自治体営業を実施する際は、人脈やコネに頼らず、自社の強みを活かした営業活動を行うことが大切です。
加点方式ではなく減点方式で評価されるため
自治体が新たに企業の商品・サービスを導入する場合、予算は税金が捻出されます。そのため、どれだけ高品質な提案をした場合でも、導入後に損失が出ないためにも減点方式で評価されます。
完全にリスクやデメリットを払拭できない場合、営業力があっても契約できないことがほとんどです。また、自治体営業では、リスクを最小限に抑えた提案が求められています。
入札・プロポーザル制度の仕組みが複雑なため
自治体営業を行う際は、入札・プロポーザル制度の仕組みを理解する必要があります。
自治体営業では、主に以下の入札方式とプロポーザル制度があります。
- 一般競争入札:幅広く参加者を募って一番有利な条件を提示した業者と契約する入札方式のこと
- 指名競争入札:自治体があらかじめ選んだ特定の業者だけを対象に行う入札方式のこと
- プロポーザル方式:価格の安さではなく提案内容の質で業者を選ぶ入札・選定方式のこと
自治体営業を行う際は、上記のような必要な知識を理解しておくことが大切です。入札・プロポーザル制度の仕組みを把握することで、適切な営業活動を行えるでしょう。
自治体営業を成功させるためのポイント


自治体営業を成功させるためのポイントは、主に以下の通りです。
- 入札情報や予算計画の情報収集や分析を行い対策する
- 営業を行う前に自治体のニーズを可視化しておく
- コンプライアンスを徹底遵守した上で営業活動を行う
- 価格の安さよりも品質の高さや安全性を重視して提案する
これから自治体営業を成功させたいと考えている企業は、上記を参考にしてみることがおすすめです。また、自治体営業の特性を理解し、適切な営業活動を行うことが成功への近道となるでしょう。
自治体営業が難しいと感じるなら「自治体営業プラス」がおすすめ!


「自治体営業は難しいか?」について書いてきました。
行政や公務員は必要以上に特殊化されているように感じていますが、自治体営業も同様です。
私個人的には「法人営業で活躍できる人は、自治体営業でもバッチリ活躍できる」と考えています。
官民のギャップに焦点があたる世の中ですが、少しでも自治体営業にチャレンジする方が増えたら嬉しいなと思います。
自治体営業で職員の方とやり取りする上で意識していることの記事などもありますので、併せてご覧いただけたら幸いです。
- URLをコピーしました!